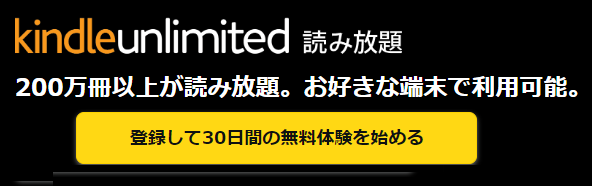いづくにか船泊すらむ安礼の崎こぎ回み行きし棚無し小舟
高市黒人の有名な和歌、代表的な短歌作品の現代語訳と句切れと語句、黒人の短歌の特徴と合わせて解説します。
黒人の羈旅歌の詩情豊かな抒景歌の中でも、とりわけ愛吟される名歌です。
スポンサーリンク
いづくにか船泊すらむ安礼の崎こぎ回たみ行きし棚無し小舟
読み:いづくにか ふねはてすらん あれのさき こぎたみゆきし たななしおぶね
作者と出典
高市黒人 万葉集1巻・58
現代語訳
今、安礼の崎のところを漕ぎめぐっていった、あの舟棚の無い小さな船はいったいどこに泊まるのだろうか
万葉集の原文
何所尓可 船泊為良武 安礼乃埼 榜多味行之 棚無小舟
句切れ
「ふねはてすらん」で 2句切れ
語彙と文法
・いづく…いづこ どこ の意味
・船泊てすらむ…「船泊て」は名詞 そのあとに「する+らむ(未来の推量の助動詞)
・安礼の崎…参河(みかわ)の国、つまり愛知県の岬 場所ははっきりしていない
・漕ぎ回(こぎた)みゆきし… 漕ぎ回む は動詞 「行く」を付けた複合動詞
・ゆきしの「し」は、過去の助動詞基本形「き」の連体形
・棚無し小舟…舟棚のない小さい船、簡素な丸木舟をいう
解説と鑑賞

高市黒人の有名な、代表的な作品の一つを解説します。
高市黒人の歌は羈旅(きりょ)歌と言われるもので、つまり旅の歌である。
ここでは海を行く船の行方についてであるが、黒人自身も、旅の途にあって詠んだ歌であり、自分のその時の状況ともかかわりが深く、ほぼ同一のことであっるといってもいい。
根底には、旅先の心細い、寂しい気持ちが、この船の行方を思わせたのだろう。
万葉集3の歌には、「旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船(ぶね)沖に榜ぐ見ゆ 3.270」との、自分を主語にして、「旅にしてもの恋しきに」と状況と心境をの主観wお率直に詠んだものがある。
ただし、この歌は、「私=われ」の限局的なものにとどまらない普遍性を持つといえるだろう。
棚無し小舟の寂寥と不安
岬を過ぎて、視界から消えていった小舟は、立派な船ではなく、素朴な船であり、だからこそ海の遠くに見えなくなってしまって、その行方が気がかりになる。
その心細さは、やはり旅の途にある人だからこそ感じるものだろう。それが旅の寂寥感である。
高市黒人独特の「孤愁」
このような寂寥感と、漠然とした不安は、万葉集の他の歌には見られない、黒人に特有のめずらしいものでもある。
そして黒人のそれを積極的に歌に訴えるではない、読み手とのある種の距離感、これが、黒人のの歌を単なる寂寥というのではなく、孤独に裏打ちされた寂寥、「孤愁」と呼ばれるゆえんだろう。
過ぎ去るものを見送るテーマ
この船のように、過ぎ去るものを見送る歌が多いこと、さらに、柿本人麻呂の跡に続いた歌人であることを重ねて、佐佐木幸綱が黒人を「遅れてきた人」と読んだことが伝わっている。
妹や家が現れない歌
また、黒人の歌には、故郷にある家族、妹や家のことは歌われないということもまた特徴の一つである。
離れたところにある故郷をポイントに歌うのではなくて、今あるとk路旅そのものの不安が立ち現れるのも黒人の歌の特徴であり、それが、人の生へのありようと重なっていくのである。
斎藤茂吉の『万葉秀歌』の評
この歌は旅中の歌だから、他の旅の歌同様、寂しい気持ちと、家郷(妻)を思う気持ちと相まつわっているのであるが、この歌は客観的な写生をおろそかにしていない。
そして、安礼の崎といい、棚無し小舟といい、きちんと出すものは出して、そして「いづくにか船泊てすらむ」と感慨をもらしているところにその特色がある。
歌調は、人麻呂ほど大きくはなく、「すらむ」などといっても、人麻呂のものほど、流動的ではない。結句の「棚無し小舟」のごとき、四三調の、名詞止のあたりは、すっきりと緊縮させる手法である。
--以上『万葉秀歌』より