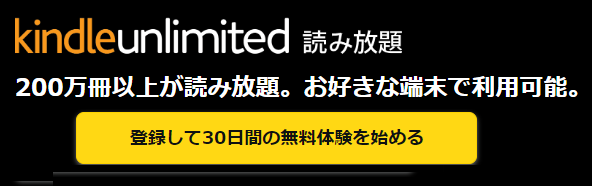「スイカの日」にちなみ、今日の日めくり短歌は西瓜を詠んだ短歌をご紹介します。
7月27日は西瓜の日

スポンサーリンク
きょう7月27日は西瓜の日。
夏が西瓜の季節であるのはわかりますが、なぜ27日なのかというと、スイカの特徴である縦の縞模様を、”綱(つな)”に例え、7月27日を「なつのつな」(夏の綱)の語呂合わせで制定されたということだそうです。
「727」の数字を並べてみると、視覚的にもいい感じですね。
関連記事:
夏休みに作る短歌 中学生の宿題に役立つ作り方の例
正岡子規の西瓜の俳句
有名な歌人でいうと、正岡子規は西瓜が好きだったそうなのですが、詠まれたのは、短歌でなく俳句だけだったようです。
横町や祇園祭の西瓜店
もてなしや池へ投げ込む冷し瓜
越し絵を照らす西瓜の灯篭かな
正岡子規の短歌記事一覧は
正岡子規の短歌代表作10首 写生を提唱
やや暑き山の日ざかりの心よく大き西瓜をわりにけるかも
作者はアララギの歌人古泉千樫(こいずみちかし)。歌集 『靑牛集』より。
人が集まったときでしょうか。気持ちよく大きな西瓜を割って、そのあとはおそらく皆で分け合う様子が詠まれています。
西瓜割れば赤きがうれしゆがまへず二つに割れば矜らくもうれし
アララギの長塚節は農家出身。スイカの色、そして、きれいに二つに割れた時の美味しそうな様子を喜ぶという素直な描写です。
わがそばに克琴といふ小婦居り西瓜の種子を舌の上に載す
斎藤茂吉 『連山』より
克琴の読みは「クーチン」。おそらくは少女のあどけない様子。
中国に旅した時の旅行詠です。
葡萄をばよろこびとりて惜しみつつ西瓜おきたるを長くと思ひき
作者は土屋文明。
おそらく自家栽培の葡萄と西瓜、どちらも大切にしている様子を詠んでいます。
現代の歌人の作品で即座に思い浮かぶのは、下の作品です。
ふとももに西瓜の種をつけたまま畳の部屋で眠っています
作者は穂村弘さん。「水中翼船炎上中」にある短歌です。
この歌集は、回想の短歌がみな郷愁を誘うものとなっているのですが、この短歌も昭和レトロな雰囲気です。
今は、西瓜はカットスイカなど切られたものが主流ですが、家族の多かった時代には丸のまま買うことが多かったのです。
大きな櫛型に切ったスイカはフォークなども使わず手づかみで、今のように上品に食べるものではなかったので、部屋に種が散らばった憶えがあります。
あるいは、西瓜の種は海で遊んできた名残なのかもしれません。
子どもたちが遊び疲れて眠ってしまった、夏の光景が浮かんできます。
嫁として帰省をすれば待ってゐる西瓜に塩を振らぬ一族
もう一首の作者は本多真弓さん。歌集「猫は踏まずに」より。
昭和の食卓にあるスイカは、塩と一緒に供されるのが普通でした。
今は、「西瓜に塩」の定番も少なくなったように思います。少量のカットスイカなら、わざわざ塩を振るまでもないのでしょう。
「塩を振らぬ一族」が大時代的で面白いところです。
つまらなさうに西瓜の種は吐くなかれ ひとつのいのち一粒にあり
作者:小池光
西瓜の種を題材にしています。下句に作者の発見があります。
そういえば、トウモロコシや、向日葵もそうです。いずれも夏の植物の実りです。
鈴虫の籠に入れやる西瓜の皮 それもむかしの夏の思ひ出
おなじく、小池光さん。
懐かしい昭和の風景、これも今では遠い思い出となっています。
八木重吉の西瓜の詩
最後に八木重吉の詩をあげておきます
西瓜をくおう
西瓜のことをかんがえると
そこだけ明るく 光ったようにおもわれる
はやく 喰おう ー八木重吉ー
八木重吉は4人家族。
皆で分け合うスイカは夏の楽しみの一つであったのです。
今日の日めくり短歌は、西瓜の日にちなむ俳句と短歌、詩をお届けしました。
日めくり短歌一覧はこちらから→日めくり短歌