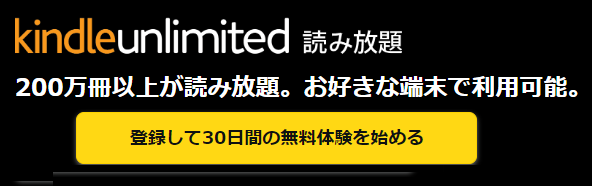秋草の直立つ中にひとり立ち悲しすぎれば笑いたくなる
作者は歌人道浦母都子の教科書掲載の短歌の解説、鑑賞を記します。
秋草の直立つ中にひとり立ち悲しすぎれば笑いたくなる の解説
読み:あきくさの すぐたつなかに ひとりたち かなしすぎれば わらいたくなる
作者と出典
道浦母都子 歌集『ゆうすげ』
現代語訳と意味
秋の草草がまっすぐに立っている中に私も一人で立っていて、おぼえる悲しみが度を越して強くなると笑いたくなるものよ
句切れと表現技法
- 句切れなし
- 文語定型
- 表現技法は特になし
注意:「秋草」には季節を表す言葉が入っていますが、短歌には季語は必要ありません。
季語が必要なのは俳句だけなので、よってこの句は季語とはいえないのです。
解説
現代の歌人、道浦母都子の代表作短歌の一つ。
学生運動の歌人として有名な歌人ですが、この歌はその後の生活の中で詠まれました。
「直立つ」の読み
直立つの読みは「すぐ」立つ。
直ぐはまっすぐの意味です。
秋草はどんな草
秋草とはおそらくススキのようなやや高い草であったかもしれません。
そのような草に紛れて作者自身も草の一本であるかのように、立っている。
他からの視線を遮るような状況にあって、悲しみを表出してもいいと思うと、それまでこらえていた胸の中の悲しみがあふれてくる。
そういう状況であったと想像できます。
悲しみへの反応
そこで、「悲しみ」とくれば、次の反応は、泣いたり嘆いたりするというのが普通ですがそうではない。
そんな簡単な悲しみではない、あまりにも深く泣いたくらいでは解消できない悲しみ、そのような圧倒的な感情のただなかに合っては、起こることは「笑う」ことだというのがこの歌のポイントです。
悲しいことがあまりにも大きいということは誰にでも理解できることではありません。
おそらく作者にとってもそうであったでしょう。
自分の思わぬ反応に、作者自身も驚いた、その体験が歌として詠まれたのです。
文語定型
道浦の短歌は文語で詠まれていますので、この歌も文語定型です。
「すぐ立つ」は文語の言葉遣いですが、結句の「笑いたくなる」というのはその部分は口語としても読めます。
つまり、「笑いたくなる」は作者の真情をストレートに表した言葉であるという印象が強いのです。
秋草の野
「秋草の」は季節はそのまま秋であり、草は、一部が立ち枯れているのでしょう。
荒涼とした風景にひとつになったときに、自分の心の中の悲しみを見つめる時間ができ、その中でふと笑いたくなったことで、逆に悲しみが「度を越している」ということに昨夜は気づかれた。
そして、その気づきが新しい道への出発点となって行ったことも推察できます。
一首の背景
作者は最初の結婚は医師の夫のDVを理由に離婚しています。
結婚生活での苦労をした体験が背景にあり、おそらく「悲しみ」とはその頃の生活の反映があるのでしょうが、短歌は詩なので悲しみの内容が何かは特定する必要はありません。
特定の出来事への悲嘆であっても「悲しみ」と名詞化することで、一つの感情を普遍化し港共有することができる、それも短歌の表現の一つです。
道浦母都子のプロフィール
歌人。和歌山市生まれ。早稲田大学文学部卒業。朝日歌壇の投稿をきっかけとして歌作を始め、近藤芳美に師事する。歌誌『未来』に所属。
近年では教科書に短歌の解説を執筆したことで知られる。
歌集『無援の抒情』について
道浦母都子は大学在学中、全共闘運動に参加。
学生運動の体験を詠った歌集『無援の抒情』はベストセラーになりました。
道浦母都子の他の短歌
下の代表作は2首は特に有名な作品です。
催涙ガス避けんと秘かに持ち来たるレモンが胸で不意に匂えり
ガス弾の匂い残れる黒髪を洗い梳かして君に逢いゆく