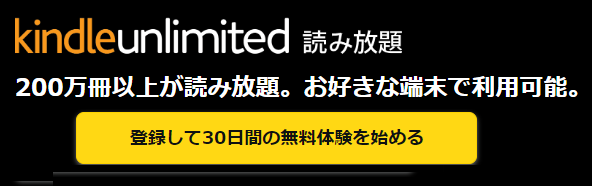石麻呂に我れもの申す夏痩せによしといふものぞ鰻とり食せ
きょうは土用の丑の日、丑の日に食べるとされる鰻の和歌は万葉集にも見られます。
きょうの日めくり短歌は、大伴家持の鰻の和歌をご紹介します。
スポンサーリンク
土用の丑の日とは
きょうは土用の丑の日。
土用の丑の日は、土用の間のうち十二支が”丑の日”という意味です。
きょうがその丑の日に当たります。丑の日と言えば、鰻なのですが、鰻の和歌の歴史は古く、万葉集の中にもあります。
石麻呂に我れもの申す夏痩せによしといふものぞ 鰻とり食せ 大伴家持【日めくり短歌】https://t.co/gp7ewXRWn8 pic.twitter.com/w1hq8MVehA
— まる (@marutanka) July 20, 2020
石麻呂に我れもの申す夏痩せによしといふものぞ 鰻(むなぎ)とり食(を)せ
いわまろに われものもうす なつやせに よしというものぞ うなぎとりおせ
作者と出典
作者:大伴家持
―万葉集巻16‐3853
「鰻」は古来は「むなぎ」
「鰻(うなぎ)」は古来は「むなぎ」と呼ばれていました。
これについて
・「ナギ」は「ナガ(長)」に通じ「ム(身)ナギ(長)」の意である
・家屋の「棟木(むなぎ)」のように丸くて細長いから
などの説があり、「鰻 うなぎ」は「長い」ことに由来があるとされています。
「鰻」の和歌の作者は大伴家持
万葉集のウナギを詠んだ和歌として有名なこの歌の作者は大伴家持(おおとものやかもち)。
大伴家持は元号令和の元になった「梅花の歌32首」の序文の作者、大伴旅人(おおとものたびと)の子どもであり、万葉集の編纂に関わった人物とされています。
万葉集の代表的な歌人の一人です。
鰻の和歌の意味
一首の意味は、
石麻呂に私は申します。夏痩せに良いという、鰻を採って、お食べなさい
というもの。
親切な助言のようですが、この歌を含む2首には「痩せたる人を笑う歌二首」と詞書が記されています。
石麻呂という人がたいへん痩せていたためですが、続く歌をみると、大伴家持がからかっていることがわかります。
痩す痩すも生けらばあらむを将(はた)やはた鰻を漁ると河に流れな
巻16‐3854
「はた」は、「ひょっとして」の意味で、この訳は
餓鬼のように痩せてはいても、生きているなら結構なこと。ひょっとして、鰻を採ろうとして川に流れなさるな。
この二首目が加わると、歌の性格がはっきりしますね。
鰻を食べるのは万葉の時代から
万葉集の時代から、鰻は食べられており、しかも滋養のある食べ物とされていました。
なので、痩せている石麻呂に対して、上のような勧めがあったのは、これは冗談ではなく、当時から既にそのように思われていたということの記録でもあります。
ちなみに、鰻はこの頃は、「うなぎ」ではなく「むなぎ」の由来は「長い」という鰻の形に由来します。
それにしても、大伴家持は茶目っ気のある人物でもあったようで、人柄がうかがえる楽しい歌でもあります。
関連記事:
万葉集とは何か簡単に解説 一度にわかる歌人と作品
大伴家持の歌一覧
- 春の野に霞たなびきうら悲しこの夕かげに鶯鳴くも
- うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば
- 万葉集の最後の歌
- 新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(よごと)
- あしひきの山さへ光り咲く花の散りぬるごとき吾が大王(おおきみ)か
- ひさかたの雨の降る日をただ独り山辺にをればいぶせかりけり
- ふりさけて三日月見れば一目見し人の眉(まよ)引き 思ほゆるかも
- 珠洲(すす)の海に朝開きして漕ぎ来れば長浜の浦に月照りにけり
- あぶら火の光に見ゆる我が縵(かづら)さ百合の花の笑まはしきかも
- 天皇(すめろぎ)の御代栄えむと東なるみちのく山に金(くがね)花咲く
- この見ゆる雲ほびこりてとの曇り雨も降らぬか心足(だ)らひに
- 雪の上に照れる月夜に梅の花折りて送らむ愛(は)しき子もがも
- 春の苑紅にほふ桃の花下照る道に出立つをとめ
- 見まく欲り思ひしなへにかづらかげかぐはし君を相見つるかも
- 石麻呂に吾れもの申す夏痩せによしといふものぞ 鰻(むなぎ)とり食(を)せ
一覧解説ページ
今日の日めくり短歌は、大伴家持の鰻の短歌を紹介しました。
日めくり短歌一覧はこちらから→日めくり短歌