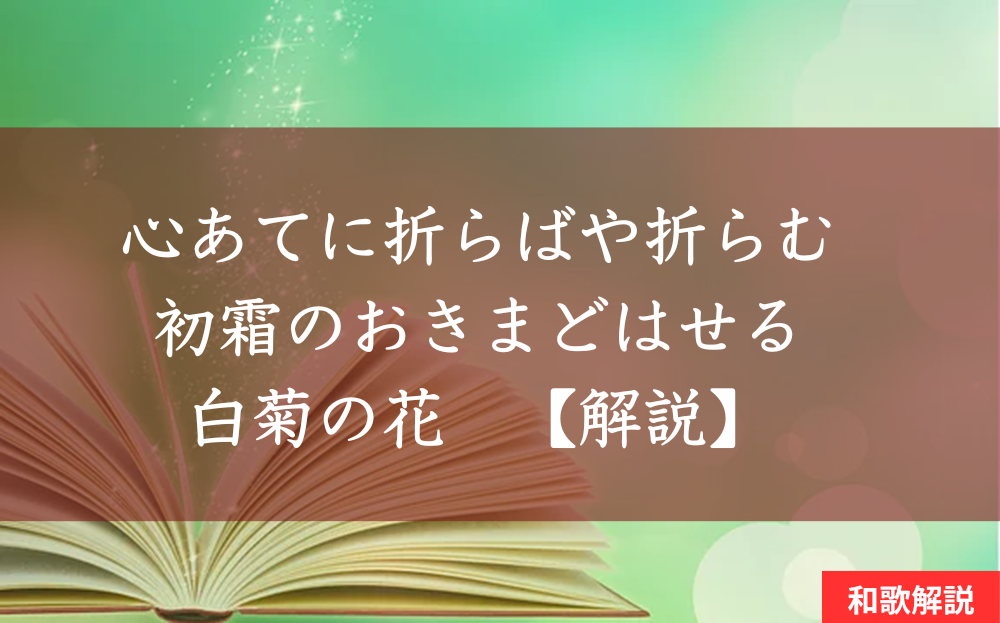
心あてに折らばや折らむ初霜のおきまどはせる白菊の花
凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の、百人一首にも採られた古今和歌集所収の有名な和歌、現代語訳と修辞法の解説、鑑賞を記します。
スポンサーリンク
心あてに折らばや折らむ初霜のおきまどはせる白菊の花 解説
読み:こころあてに おらばやおらん はつしもの おきまどわせる しらぎくのはな
作者と出典
作者:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)
出典:古今集 秋下・277 百人一首 29番
現代語訳と意味
心して見定めておるなら折れるだろうか。初霜が一面に下りて、その白さで霜か菊かと惑わせる白菊の花を
句切れ
2句切れ
語と文法
新説を含めて、語の解説を記します。
心あてに・・・「よく注意して、」「慎重に」
「心あてに」は「よく注意して、」「慎重に」の意味。
「心あてに」は以前は、「あて推量に」「あてずっぽうに」などの意味の副詞つぃて訳されることが多かったが、その後、新しい説により、解釈が改められた。
おらばやおらむ
・おらばや…「や」はまどいから来る軽い疑問の表現 (反語の説もあり)
・「む」は意志の助動詞で上の「や」と係り結び
係り結びの解説
係り結びとは 短歌・古典和歌の修辞・表現技法解説
をきまどわせるの品詞分解
・おき…「霜が置く」。
ものの上のいただきに霜がおりていることを「霜が置く」という
・まどわせる…「まどう+す(使役の助動詞)」
他のものになにかをさせることをいい、「~せる(させる)」と訳す
修辞と表現技法
・「や…む」は係り結び
・「おらばやおらむ」の繰り返しは折るか折るまいかの迷いをそのまま表現するために言葉を重ねて、下句の「まどはせる」につなげる
・菊を霜と見立てるのは漢詩にある表現
解説と鑑賞
凡河内躬恒の特徴である、四季歌の一首。
季節の変化とその寒さを歌うもの。その朝気がついた「初霜」で冬への移ろいを表します。
まだ変わらず見られると思っていた菊の花にいつの間にか霜がおりて、冬の到来を思わせる。
「おきまどう」で季節の変化に迷っているのは、実は作者の方で、白い菊の花の方は、霜をかぶりながらも霜と違わぬ純白を保って美しに咲いているという情景です。
「初霜+菊」の視覚的な効果
「初霜」を詠むだけではなく、同じ色の「白菊」を重ねると、「白」の視覚的な印象が強まる効果があります。
「おらばやおらむ」の歌の調べは文字通り、おろおろするような、戸惑いを強調して表し、「おきまどわせる」で長めに音調を取り、結句を体言止めの「白菊の花」できっちり落ち着かせる構成です。
「おらばやおらむ」「おきまどわせる」の「お」の連続の歌の調べも味わうべきところです。
この歌の2つの解釈の違い
この歌のポイントは、初句の「心あてに」の語の意味の理解と、そこからの作者の真意の理解にあります。
「心あてに」の訳し方
この歌はの最初の「心あてに」は「当て推量に」「あてずっぽうに」と訳されており、これまでは間違った理解がされているものがありました。
それまでの訳:
もし折るのなら、当て推量で折ろうか。初霜が一面に下りて、その白さで霜か菊かと、人を惑わせる白菊の花を
正しい訳:
心して見定めて折るなら折れるだろうか。初霜が一面に下りて、その白さで霜か菊かと、人を惑わせる白菊の花を
上句の迷う理由は下句にあり、霜も菊の花も同じように白いことがその理由というのが、歌の表層ですが、作者の真意はそれだけではありません。
この和歌の魅力の解明
初句の訳し方によって歌の全体の理解がまったく違ったものになってきます。
「初霜が置くなか、いっそう白さを際立たせて咲く白菊。ぜひにも折り取りたいが、その凛としたこの世ならぬ美しさは、どうしても手を触れるのをためらわせる。その美を、錯視とためらいの身振りの表現によってかろうじてわがものにして見せたのである」と評し、この歌の魅力を解き明かした。(『百人一首-編纂が開く小宇宙』田渕句美子著 訳部分は渡部泰明)
初句「慎重に折り取るならば」は「比喩ではなく韜晦された讃美の表現」(田渕)と読み取るべきなのです。
実際には、見分けがつかないほど白いわけではなく、作者の真意は折るのをためらわせる、白菊の美しさにあります。
作者はこの菊を折るには至っておらず、「錯視とためらいの身振りの表現によってかろうじてわがものにして見せた」、つまり上のような歌を詠むことで、この菊の美しさを自分の言葉で表す=手中にしたと言えます。
当時、この歌は正しく理解されており、藤原俊成と藤原定家にも評価されていました。
しかし、その後初句が「あてずっぽうに」と理解されるようになってから解釈が変わってしまいました。
初句の種々の解釈
正岡子規は、この歌の初句を「あてずっぽうに」の意味の方で以下も文字通りに理解し
一文半のねうちも無之(これなく)駄歌に御座候。此歌は嘘の趣向なり。初霜が置いたくらいで白菊が見えなくなる気遣無之候(これなくそうろう)。
と酷評しています。
他にも、佐佐木幸綱は、この歌について
躬恒の歌は、全部が真っ白で、影さえも白い極端な世界を思い浮かべる遊び心の歌である。(中略)興味の中心は、極限的な季節の境界にあり、現実を超えて極限的な白一色の幻想世界にあるのだ
と述べていますが、これはあくまで菊と霜が白いことを文字通りにとらえており、こちらも初句を「注意深く慎重に」と訳した場合とは違った見解となっています。
凡河内躬恒の他の歌
春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やは隠るる(古今41)
雪とのみ降るだにあるを桜花いかに散れとか風の吹くらむ(古今86)
花見れば心さへにぞうつりける色には出でじ人もこそ知れ(古今104)
住の江の松を秋風吹くからに声うちそふる沖つ白波(古今360)
作者凡河内躬恒について
凡河内躬恒(おほしかふちのみつね) 生没年不詳
平安時代中期の歌人。三十六歌仙の一人、『古今和歌集』の撰者。紀貫之(つらゆき)につぐ60首の歌がとられている。
感覚の鋭い清新な歌風で叙景歌にすぐれ、即興的な歌才に優れていたことをうかがわせる。
四季歌を得意とし、問答歌などでは機知に富み、事象を主観的に把握して、平明なことばで表現するところに躬恒の特長がある。
