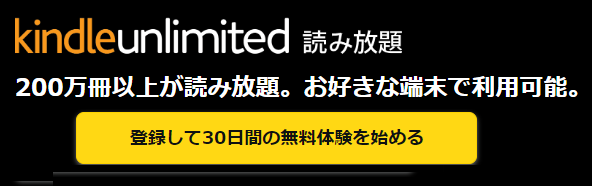道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ
西行法師(さいぎょうほうし)の代表作として知られる、新古今和歌集の有名な短歌の現代語訳、品詞分解と修辞法の解説、鑑賞を記します。
この短歌の柳は、後に松尾芭蕉も俳句にした「遊行柳」と呼ばれています。
スポンサーリンク
道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ
読み: みちのべに しみずながるる やなぎかげ しばしとてこそ たちどまりつれ
作者と出典
西行法師(さいぎょうほうし)
新古今和歌集 262 他に「西行法師歌集」
現代語訳と意味
道のほとりに清水が流れている、そのそばの柳の木陰よ、ほんのちょっとと思って立ち止まったのであるが
西行の他の短歌
西行法師の有名な和歌 代表作7首と歌風の特徴
句切れ
3句切れ
語句と文法
- 道のべ・・・道のわき 「べ」は辺、「何々の辺り」の意味
- 清水・・・地面や岩の間などからわき出るきれいに澄んだ水を差す
- 流るる・・・「流る」が基本形 その連体形
- 柳かげ・・・柳の木の木陰の意味
「しばしとてこそ」の品詞分解と意味
・しばし・・・「しばらく」「ちょっとの間」の意味
・とて・・・
・こそ・・・下に逆説の意味を伴う
「こそ~つれ」が「係り結び」
「こそ」で、反対の意味を暗示して続くため「長居をしてしまった」ことが推測される
「立ちとまりつれ」の品詞分解と意味
・つれ・・・完了の助動詞「つ」の已然形 「した、してしまった」の意味
※「こそ」は已然形と結びつくので、「つれ」は已然形
係り結びの解説
係り結びとは 短歌・古典和歌の修辞・表現技法解説
解説と鑑賞
西行の代表的な和歌作品の一つとして広く知られている作品で、すがすがしく素直な内容となっていて古くから愛吟される歌です。
旅の途中の道のほとりに、日差しを遮る大きな柳がある。その脇には、澄んだ水が流れており、おそらく飲むことができたのでしょう。
旅の時は、先に進むのが日々の仕事であるのですが、風がそよぐ柳の葉、日差しを遮る涼しい空間とさらさらと流れる水の眺めがこころよく、ちょっとのつもりが、そこでゆっくりとくつろいでしまったというもの。
一首全体が一枚の絵のように、美しいものとしてまとまっているのは、長居を誘うほど、快い空間であると示されているためです。
結句の已然形も、きっちり止めたものよりも、余韻があり、旅の余情を思わせます。
西行と芭蕉の「遊行柳」
この柳は栃木県那須郡那須町大字芦野にあった柳で、「遊行柳」と呼ばれ、のちに松尾芭蕉も俳句に詠みました。
松尾芭蕉の「奥の細道」から
清水ながるゝの柳は、蘆野の里にありて、田の畔に残る。此所の郡守戸部某の、「此柳みせばや」など、折をりにの給ひ聞え給ふを、いづくのほどにやと思ひしを、今日此柳のかげにこそ立より侍つれ 。
田一枚植て立去る柳かな
(たいちまい うえてたちさる やなぎかな)
-「奥の細道」
上の「清水ながるゝの柳」というのが、この西行の歌を指しています。
「遊行柳」の場所
〒329-3443 栃木県那須郡那須町大字芦野
西行法師について
西行法師 1118年~1190年
俗名は佐藤義清(のりきよ)
北面の武士であったが、23歳で出家。法名は円位(えんい)というもので、西行は雅号。
生涯を通じで諸国を行脚し、仏道修行と歌作に専心した。
藤原俊成(しゅんぜい)と並ぶ平安時代の代表的な歌人。
新古今和歌集とは
新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)は、鎌倉時代初期に編纂された勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう)。
天皇や上皇の命令により編集された、代表的な和歌集の一つ。