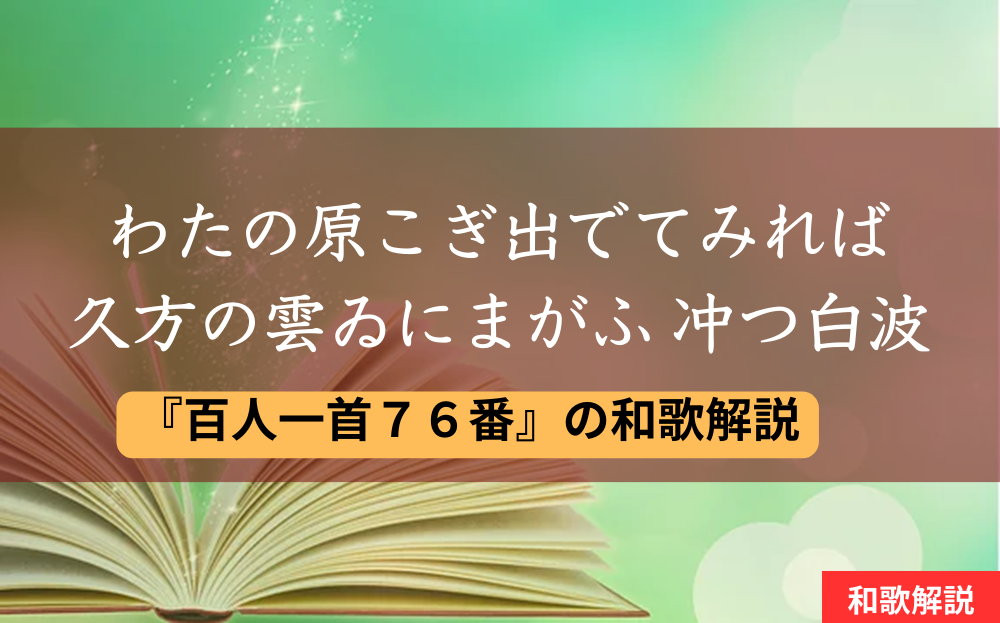
わたの原 こぎ出でてみれば 久方の 雲ゐにまがふ 冲つ白波
百人一首76番 法性寺入道前関白太政大臣の和歌の現代語訳と一首の背景の解説を記します。
スポンサーリンク
わたの原 こぎ出でてみれば 久方の 雲ゐにまがふ 冲つ白波
読み:わたのはら こぎいでてみれば ひさかたの くもいにまごう おきつしらなみ
作者と出典
百人一首76番 法性寺入道前関白太政大臣
現代語訳と意味
大海原に漕ぎ出てみると、天の雲かと思われるほどの沖の白波よ
・・・
語と句切れ・修辞法
一首に使われていることばと文法と修辞法、句切れの解説です
句切れと修辞法
- 句切れなし
- 体言止め
語句の意味
・わたの原…「わた」は海のこと。大海原
・ひさかたの…枕詞
。雲ゐ…読みは「くもい」漢字は雲井で、空の高い所。 大空。 天上の意味
・まがふ…「見まごう」に同じ。見間違えるほどの
・沖つ…「沖の」に同じ。「つ」は「の」の意の格助詞。意味は「沖の白波」
関連記事:
百人一首の枕詞が使われた和歌6首 現代語訳と解説
解説
海と空に共通する雲と波を使って、雄大な情景を詠んだ名歌。
詞書には
新院位におはししまし時、海上遠望ということをよませ給いけるによめる
とある・
「雲い」は雲の住まいである空をさす言葉だが、ここでは単に雲の意味に用いられている。
本歌は 新古今集の藤原重貞の
「なごの海のかすみの間よりながむれば入る日をあらふ沖つ白波」
とされる。
法性寺入道前関白太政大臣について
法性寺入道前関白太政大臣は藤原忠通のことです。
藤原忠通(ふじわらのただみち)1097-1164
平安後期の公卿。白河法皇に罷免された父にかわり,関白,摂政,太政大臣を歴任。従一位にいたる。鳥羽(とば)院政で復権した父と権力をあらそい,保元(ほうげん)の乱の一因をつくった。詩歌にすぐれ,書は法性寺(ほっしょうじ)流と称される
百人一首の前の歌
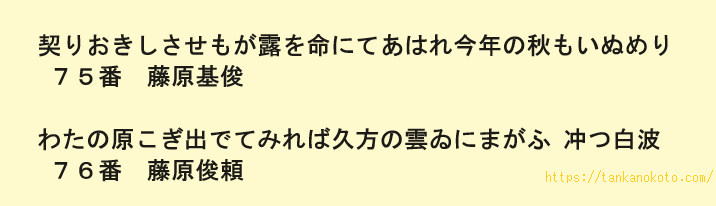
この歌の前の歌と藤原忠道のエピソードは
契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり【百人一首75】
