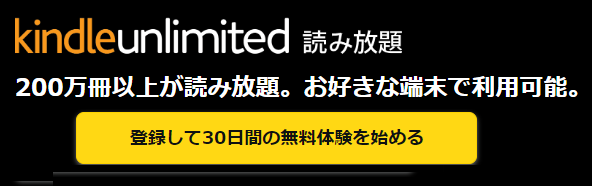藤原良経は、新古今集を代表する歌人と言われています。
きょうの日めくり短歌は、忌日3月7日(4月16日) にちなみ、藤原良経の百人一首の和歌とその他代表作秀歌をご紹介します。
スポンサーリンク
藤原良経とはどんな歌人
藤原良経は、新古今集を代表する歌人です。新古今集と言えば藤原定家をまず思い浮かべる人が多いと思うのですが、実は良経の方を優れた歌人とする人も多くいます。
歌人の塚本邦雄は、定家よりも、「良経が好き」であると、講演集を掲載した『新古今新論』の中で述べています。
藤原良経の和歌の特徴
藤原良経の和歌の特徴を一言でいうと、気品の高さがまずあげられます。
もう一つが、歌の多くが諦観に裏打ちされているところです。これは多く下に述べる良経の境遇によるとゐます。
そして、定家のような妖艶さはなく、巧みに走る傾向もみられません。思ったままを詠んだように見えます。
つまり、定家とは違う種類の天性の才能があったといえるでしょう。
藤原良経の業績
藤原良経の業績としてあげられるのは、まず、新古今集を編纂したこと、「仮名序」を記したことで知られています。
もう一つは、「花月百首」「六百番歌合」など多くの歌合を主催したこと。
これらは、新古今集の編纂につながり、新古今調という和歌の新しい流れを作りました。
藤原良経の境遇
まず、良経が九条家を継いだのには、兄良通が 22歳で早世したことにあります。
さらに、父関白兼実が失脚、良経自身も蟄居を余儀なくされます。
このような、自分の力ではいかんともしがたい政変に巻き込まれことが、虚無感を漂わせる歌になった理由の一つかもしれません。
良経は、その後政界に復帰しますが、38歳の時に、原因不明のまま亡くなっています。
死因はよくわかっていませんが、夜眠っているときに亡くなったそうです。
いかに昔とはいえ、短い生涯と言わざるを得ません。
藤原良経の代表作
代表作として挙げられるのは、百人一首のきりぎりすの歌として知られる、下の和歌です。
きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき ひとりかも寝む
読み:きりぎりす なくやしもよの さむしろに ころもかたしき ひとりかもねん
作者と出典
作者:後京極摂政前太政大臣(ごきょうごくせっしょうさきのだいじょうだいじん)
出典:百人一首91番 新古今集 518
現代語訳:
こおろぎが鳴く霜の降りた夜の寒々とした筵の上に衣の片袖を敷いて、一人寂しく寝るのだろうか
後京極摂政前太政大臣は、藤原良経のことです。
※詳しい解説
きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む 後京極摂政前太政大臣
もう一首は、新古今の巻頭歌として、下の歌が有名です。
み吉野は山も霞みて白雪のふりにし里に春はきにけり
読み:みよしのは やまもかすみて しらゆきに ふりにしさとに はるはきにけり
作者と出典
作者:藤原良経=後京極摂政前太政大臣(ごきょうごくせっしょうさきのだいじょうだいじん)
出典:新古今和歌集1 巻頭歌
現代語訳:
吉野は山も霞んで、少し前まで白雪の降っていた里に、春がやって来たのだなあ
※解説記事:
み吉野は山も霞みて白雪のふりにし里に春はきにけり 藤原良経
かぢをたえ由良のみなとによる舟のたよりも知らぬ沖つ潮風
読み: かじをたえ ゆらのみなとに よるふねの たよりもしらぬ おきつしおかぜ.
作者と出典
九条良経 (藤原良経)
新古今和歌集 巻11 恋歌1 1073
舵を失ってう由良の港に寄ろうとする舟のように 漕ぎ寄る手段もわからない。沖の潮風よ吹いておくれよ
※解説記事
かぢをたえ由良のみなとによる舟のたよりも知らぬ沖つ潮風 九条良経
藤原良経の他の和歌
新古今集より
おしなべて思ひしことの数々になほ色まさる秋のゆふぐれ
幾夜われ波にしをれて貴船川袖に玉散る物思ふらむ
いさり火のむかしの光ほの見えてあしやの里にとぶ蛍かな
わすれじと契りていでしおもかげは見ゆらむものをふるさとの月
うちしめりあやめぞかをる時鳥鳴くや五月の雨の夕暮
人住まぬ不破の関屋の板廂荒れにしのちはただ秋の風
あすよりは志賀の花園まれにだに誰かは問はむ春のふるさと
その他の歌集から
見ぬ世まで思ひのこさぬながめより昔にかすむ春のあけぼの 風雅集
ながむればかすめる空のうき雲とひとつになりぬかへる雁がね 千載集
かすみゆくやどの梢ぞあはれなるまだ見ぬ山の花のかよひぢ 千載集
散りはてむ木の葉の色を残しても色こそなけれ峰の松風