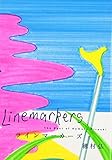穂村弘さん、現代短歌を結社を越えてけん引する一人といっていい歌人ですが、その短歌にはどのようなものがあるでしょうか。
穂村弘さんの短歌代表作とその作風の特徴をご紹介します。
スポンサーリンク
穂村弘の短歌代表作
穂村弘の短歌でよく知られているのは、やはり、最も最初の歌集にある初期の作品だと思います。
今では口語短歌は広く知られており、一般的な短歌のスタイルのひとつになっていますが、当時は斬新な印象があったためです。
中でももっともよく引用されたのは下のような歌です。
サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい
ハロー 夜。ハロー 静かな霜柱 ハローカップヌードルの海老たち。
「酔ってるの?あたしが誰かわかってる?」「ブーフーウーのウーじゃないかな」
一首目も二首目も共に、文章としてのつながりよりも、単語の羅列で成り立っていることが、一度読むとすぐわかります。
3首目は、会話がそのまま歌となっています。
一つの文にはなっていない、このような短歌は当時はたいへんめずらしかったのです。
また、これらの短歌は、言葉の意味は難しくありませんが、一度読んだだけでその意図がすぐにわからないところがあります。
ある意味、平易な言葉で詠まれた韜晦的でもある独特の作品なのです。
穂村弘の短歌の特徴
逆に穂村さんの作品を部分的にしか読まないと、ふざけたよくわからない短歌だと思われがちですし、当初の頃はそう思っていた人が多くありました。
しかし、多数の作品の中には、これとは違った作風の作品もあります。
体温計くわえて窓に額つけ「ゆひら」とさわぐ雪のことかよ
これは恋人の仕草を詠った、、実は清新な相聞の歌です。
ほんとうにおれのもんかよ冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は
歯を磨きながら死にたい 真冬ガソリンスタンドの床に降る星
また、あえて軽い言葉で、自身の心の痛みを遠目に見たような上のような歌もあります。
ハーブティーにハーブ煮えつつ春の夜の嘘つきはドラえもんのはじまり
のような現代の風俗を取り入れた作品も得意のようです。
そして
恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の死
のような、リフレインと視覚的な印象にも訴える特異で効果的な作品。
これには、単なる効果だけではなくて、大いなる絶望感が漂います。
穂村弘の作品評
これら穂村弘の作品についての評は
破滅の頂点に至福の瞬間があることを語る。凶暴な青春の革新をとらえた。作品は現実の人生に還元されない。(「卵産む海亀の背に飛び乗って手榴弾のピン抜けば朝焼け」について 加藤治郎氏評)
他に、歌人の米川千嘉子は穂村弘の作品にある「痛ましい孤独感」を指摘します。
穂村弘の第三歌集「手紙魔まみ」の登場人物について
相対化をうけつけない感覚的な無力感、絶望感、そういうものを、作者の過剰なまでの鋭敏さと孤独感で磨きあげたところに<まみ>は生まれた
と読み解きます。
この「手紙魔まみ、夏の引っ越し(ウサギ連れ)」は、歌集のコンセプト自体が、「まみ」と「穂村弘」の対話の構成で成り立っており、語り手である一人称は、「まみ」という女性になっています。
穂村弘の短歌の特徴
穂村弘の短歌には他にも、特筆すべき特徴があります。
ひとつは抒情性、もう一つは、サディスティックな一面です。
校庭の地ならし用のローラーに座れば世界中が夕焼け
天沼のひかりでこれを書いている きっとあなたはめをとじている
穂村弘の短歌が口語ゆえにソフトな短歌だと思っていると、
閃光ののち、しましまの、うずまきの、どうぶつだけが生まれる世界
の終末思想が語られたり
嘘をつきとおしたままでねむる夜は鳥のかたちのろうそくに火を
ある種の自責、そして、さらに
窓のひとつにまたがればきらきらとすべてをゆるす手紙になった
これらの歌は、「嘘」の自責とファンタジックな「鳥」との取り合わせ、「窓のひとつにまたが」るという絵になる動作に隣り合う「ゆるす」に見られる怨嗟が見られます。
楽しい言葉があっても決して、のんきな楽しい歌ではありません。
これも穂村弘の短歌の特徴の一つであると思われます。
孤独感、アイロニー、そして、一見柔らかくソフトな言葉に並置されるマイナーな言葉は、作者のルサンチマンによるものでしょう。
それがまっすぐでないところが、より心の深いところに隠し持った作者の痛みとなって読み手に伝わるのです。
たとえば同じ口語短歌の俵万智さんや、他のニューウェーブ短歌の歌人の作品のようにストレートではない攻撃性をはらむのが穂村弘さんの短歌と言えるかもしれません。
穂村弘インタビュー
穂村さんのインタビューについては、もっとも最近のものが良くまとめられています。
穂村弘「短歌は生きるための武器」朝日新聞インタビュー beフロントランナー
他に、最近の作品については、最新歌集の『水中翼船炎上中』も必読です。
現代短歌、ニューウェーブ短歌の旗手と言われて第一線を走ってきた穂村弘さんですが、この歌集を読むと時代を回顧する作品も多くなっています。
たいへん多彩な作風の作品の他にも、短歌の分野では、現代短歌の紹介の他にも、評論や歌論関連のご著書も多く見られます。
これからも現代短歌とそれ以前の短歌の橋渡し役となって、活躍されて行っていただきたいものです。
穂村弘の歌集
- 第一歌集『シンジケート』沖積舎、1990年10月。
- 第二歌集『ドライ ドライ アイス』1992年11月。
- 第三歌集『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』2001年6月。
- 第四歌集『水中翼船炎上中』 2018年5月
他に 自選短歌集「ラインマーカーズThe Best Of Homura Hiroshi」
穂村弘について
穂村 弘 (ほむらひろし) 1962年5月21日
日本の歌人。歌誌「かばん」所属。 加藤治郎、荻原裕幸とともに1990年代の「ニューウェーブ短歌」運動を推進した、現代短歌を代表する歌人の一人。批評家、エッセイスト、絵本の翻訳家としても活動している。歌集に『シンジケート』『水中翼船炎上中』他。