ひたぶるに我を見たまふみ顔より涎を垂らし給ふ尊さ
島木赤彦の教科書や教材にも取り上げられている代表的な短歌作品の現代語訳と歌の背景、解説を記します。
スポンサーリンク
ひたぶるに我を見たまふみ顔より涎を垂らし給ふ尊さ
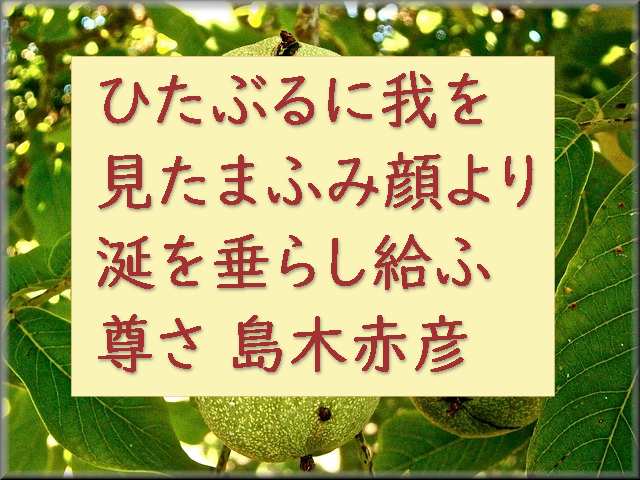
読み:ひたぶるに われをみたまう みかおより よだれをたらし たまうとうとさ
作者と出典
島木赤彦 『氷魚(ひお)』(1926年)
現代語訳と意味
一心に私を見てくださる父の顔より涎が垂れている、その尊いことよ
句切れと表現技法
・句切れなし
・体言止め
語句と文法
・ひたぶるに…いちずなさま。ひたすら
・見たまふ…「見る+たまふ 尊敬の補助動詞」漢字は「給ふ」 敬うべき父が主語で「~なさる」の意味。
・み顔…「み」は接頭語 漢字は「御顔」
定義解説
・垂らし給ふ…「垂らす+たまふ 尊敬の補助動詞」
解説と鑑賞
島木赤彦の歌集『太虚集』より、大正7年の作品。
「わが父」との題名で下の詞書がある。
6月14日早朝茅野駅下車、一里の狭道を歩みて老父を訪ふ。老父七十五、心甚(はなは)だ安静にして却りて病後の頼み少なきを思はしむ
「頼み少なき」は「長く生きられそうもない」との意味で、作者の島木赤彦はこの一連に父を題材に十七首を呼んでいる。
この歌の意味
本歌はその十七首の最初の一首で、父との対面の最初の時を歌っている。
久しぶりに訪ねてきた息子の顔から父は目を離さず、一心に見つめ続けるので口から涎が垂れてしまうのであるがそれもかまっていない。
そのような息子の訪問に強く注意を向ける父、作者の方から言うと自分の訪れを喜んでくれている父の様子がこの歌と一連を詠む動機となっていると思われる。
「ひたぶるに」の意味するもの
初句の「ひたぶるに」はそのあとの「見たまふ」にかかる副詞で、一首の内容を決める重要な言葉。
息子である作者を見つめることには、対象となる作者への強い愛情が感じられる。「ひたぶるに」はその程度を表す。
「涎を垂らす」の理由
その結果が「涎を垂らす」であり、ここで涎が垂れている理由は、父の息子への注視にある。
懸命に見つめた結果、体の他の部分への動作へ注意が向かなくなったのだろう。
また一連からは父が寝たきりに近い状態であったことがわかり、父は涎が垂れやすい不自然な姿勢、おそらくは、息子の方を向いて首と顔を横に傾けていたため涎が垂れたのであろう。
あえて作者が「涎を垂らす」と詠んだのは、それを伝えるためであり、さらにそれに「涎を垂らし給う」と敬語をつけたのは、その父の愛情を感じたためである。
死の床においても、息子である自分に愛情を向けてくれる父の思いを「尊い」と感じたからこそ、作者は老いた父の哀れな様子をもつぶさに伝えているのである。
歌の背景
この父は島木赤彦の実父だが、作者は幼少の頃母を亡くし親は父一人となっていた。
さらに、若い時に養子になって島木姓を名乗っており、稀にしか会えない父への思い入れは強かったと思われる。
一般的な父と子のつながりとは違い、肉親の縁の薄い父子であり、それゆえに父子両方の思い入れも強かったと思われる。
一連の他の歌
「わが父」の一連の他の歌は下のとおり。
青山の雪かがやけりこの村に父は命をたもちています
雪のこる高山すその村に来て畑道(はたけみち)行く父に逢はむため
かへり来し我が子の声を知りたまへり昼の眠りの眼をひらきたまふ
夏芽吹く櫟林の家のうちに命をもてる 父を見にけり
古田のくぬぎが岡の下庵にふたたびも見む父ならなくに
この真昼布団の上に座りいますわが老父は歓びに似たり
われ一人命のこれり年老いし父の涎を拭ひまいらす
父と我とあひ語ること常のごとし耳に声きく幾ときかあらむ
郭公の啼くこえ近しちちのみのちちのへに居て飯食ふ我は
間(あひだ)なく郭公鳥のなくなべに 我はまどろむ老父の辺に
川の音山にし響くまひるまの時の久しき父のかたはらに
くれないに楓芽をふく窓のうちに父と我が居るはただ一と日のみ
日のくれの床のうへより呼びかへし我を惜しめり父の心は
斎藤茂吉の「死にたまふ母」との類似
同じアララギ派歌人の斎藤茂吉は「死にたまふ母」という一連を詠んでいるが、タイトルを見てもわかるように、母に「死に給う」の尊敬語を入れており、赤彦の作品にも共通するところである。
他にも共通するモチーフがあるので、参考に見てみたい。
はるばると薬(くすり)をもちて来(こ)しわれを目守(まも)りたまへりわれは子なれば
寄り添へる吾を目守りて言ひたまふ何かいひたまふわれは子なれば
上二首は、母の枕元にかけつけて最初の対面の場面。
「目守(まも)りたまへり」は、母が作者である茂吉をじっと見つめたという意味である。
「われは子なれば」には、斎藤茂吉も子どもの頃に養子に出てしまい、母とは早く別れてしまったという島木赤彦とも共通する背景がある。
※斎藤茂吉の「死にたまふ母」を読む
島木赤彦とは
島木 赤彦(しまき あかひこ、1876年(明治9年)12月16日 - 1926年(大正15年)3月27日)は、明治・大正時代のアララギ派歌人。本名は久保田俊彦。伊藤左千夫の死去後のアララギを率い、結社として成長させた。歌論に「鍛錬道」「寂寥相」などを説いた。歌集は「切り火」「氷魚」「太虚集」他。
島木赤彦の他の代表作
夕焼け空焦げきはまれる下にして氷らんとする湖のしずけさ 島木赤彦の初期短歌代表作品
みづうみの氷は解けてなほ寒し三日月の影波にうつろふ
