隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり
島木赤彦の教科書や教材にも取り上げられている代表的な短歌作品の現代語訳と歌の背景、解説を記します。
スポンサーリンク
隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり
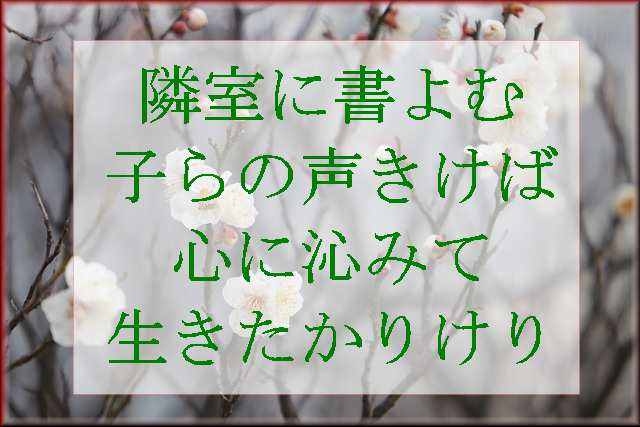
読み:りんしつに ふみよむこらの こえきけば こころにしみて いきたかりけり
作者と出典
島木赤彦 『柹蔭集』(しいんしゅう)
現代語訳と意味
隣の部屋から本を読んでいる子供の声が聞こえてくるとしみじみと生きながらえたいと思うことよ
句切れと表現技法
・句切れなし
語句と文法
・隣室に…昔の部屋は隣の部屋と衾で仕切られていることが多かったため、音がよく聞こえた
・書…「ふみ」と読む。本のこと。
・沁みて‥基本形「沁む」 意味は「深く心を寄せる」
生きたかりけりの品詞分解
・動詞基本形「生く」の連用形
・「たし」希望の助動詞の連体形「たかり」
・けり…詠嘆の助動詞「…だなあ・ことよ」などと訳す
解説と鑑賞
島木赤彦の最後の歌集『柹蔭集』より、大正15年の最晩年の作品。
「恙ありて」と題する連作の中間にあり、闘病中で状態が悪化したときに詠まれた。
一首の背景
島木赤彦は51歳の時胃がんとわかり2か月後に亡くなった。
上の歌は闘病中の作品。
島木赤彦は胃がんの宣告ののち病院には入院をせず、自宅で妻らの介護を受けていたが、余命いくばくもないことを悟っていた。
この歌の意味
昔の家は壁ではなく衾を隔てて隣の部屋がある構造となっていた。
隣の部屋には子供たちがいて、学校の教科書などを音読していたのだろう。
その声を聴いて、もう長くは生きられないと死を予感していた作者だったが、改めてやはり「生きていたい」という思いがこみ上げたという意味となる。
子どもの声は常と変わらず朗らかで、これまでの日常を思い起こされる者だったと思われる。
それに触発されて彼らと共に生きていたいという作者のはかない望みが胸を打つ歌となっている。
作者の状態
赤彦は約2か月前に不調を覚えていた胃の診察を受け、胃がんの宣告を受ける。
既に手遅れの状態で絶対安静となったが、手立てがなかったためか自宅療養となった。
次第に小食となり体にも痛みが出て、黄疸が出て苦しんでいる様子も一連に詠まれている。
宣告からわずか2カ月であったが、作者は自らの病状より十分に死を予感していた。
「生きたかりけり」の詠嘆は、その予感を前提にしたもの出る。
一連の他の歌
一連の他の歌は下のとおり。
魂はいづれの空に行くならん我に用なきことを思(も)い居り
箸をもて我妻(あづま)は我を育めり小鳥の如く口開(あ)く吾は
我が家の犬はいづこにゆきぬらむ今宵も思ひいでて眠れる
最後の歌は絶筆で、最初は「猫」と読んだが、「ちがう、犬だった」と笑って直させたということが伝わっている。
島木赤彦について
島木 赤彦(しまき あかひこ、1876年(明治9年)12月16日 - 1926年(大正15年)3月27日)は、明治・大正時代のアララギ派歌人。本名は久保田俊彦。伊藤左千夫の死去後のアララギを率い、結社として成長させた。歌論に「鍛錬道」「寂寥相」などを説いた。歌集は「切り火」「氷魚」「太虚集」他。
