列車にて遠く見ている向日葵は少年のふる帽子のごとし
教科書にも掲載されている、寺山修司の有名な短歌代表作品の訳と句切れ、文法や表現技法などについて解説、鑑賞します。
・教科書掲載の短歌一覧は↓
高校教科書の現代短歌掲載作品一覧 栗木京子,俵万智,寺山修司,大西民子
スポンサーリンク
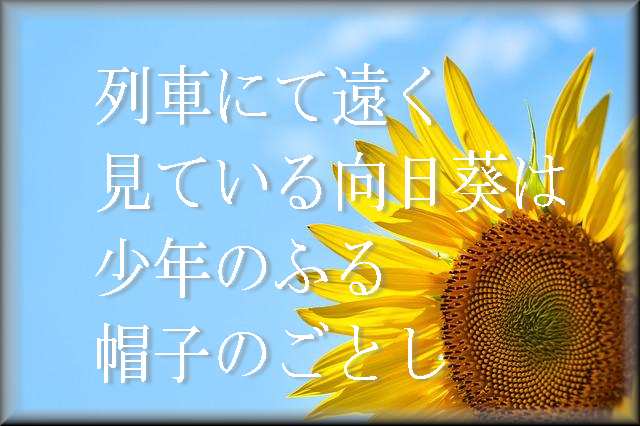
読み:れっしゃにて とおくみている ひまわりは しょうねんのふる ぼうしのごとし
作者と出典
寺山修司 「空には本」
現代語訳
電車の中から遠く離れたところに咲いている向日葵が風に揺れているのを見ると、少年のふる帽子のようだ
語と文法
・列車にて…「にて」は場所を示す格助詞
・ごとし… ~のようだ の意味
句切れ
句切れなし
表現技法
・「ごとし」の比喩が表現技法のポイント
上句は事実、下句は、そこから得た比喩を表している。
「向日葵」という夏の花、生気にあふれたものと、「少年」というこれも若々しい命の2つのモチーフとを、比喩によって一首に登場させている。
帽子は、この場合風に揺れていると思われるが、その点省略がなされている。
寺山修司の短歌一覧は→ 寺山修司の有名な短歌と教科書掲載作品一覧
一首の解説
ネットで見る限り、この歌には、作者が向日葵を見ているという説と、向日葵それ自体が遠くを見ているという説の、2通りの説明があるようです。
先生は、遠く見ているのは、「向日葵」だと考えます。これは、『列車にて』で二つに切れると考えます。
話者が列車に乗っていた。すると少年が帽子を自分に振ってくれているように見えた。しかし、それは、遠くを見ながら揺れる向日葵だったんだよという歌だと考えます。
Bさんが言ったように、もし遠くを見ているのが、話者だったなら、「遠くに見える向日葵」と書くはずだと考えたからです。
http://www4.plala.or.jp/higa/himawari.htm
「列車にて」の、「にて」は場所を示す格助詞ですが、この場合は「列車に」(口語なら「列車で」)とすると、そうすると4文字になって字数が足りないため、「にて」の助詞を使ったと考えられます。
「にて」は説明の意味が伴いますが、通常短歌では、説明を含ませるのは良くないとされます。
ともあれ「列車にて」は作者の位置を示すものですが、これを初句に置くにはそれなりの意味があり、「列車にて」に続く「遠く見ている」の主語が別々であるということは、あまり考えられません。
要は、作者のいる列車の窓からは向日葵の位置が遠いため、帽子のように思えたということなのです。
「ごとし」というのは、意識をした比喩のことであって、見間違えたというようなことではありません。
「少年のふる帽子」というのは、静止した向日葵ではなく、それが風に降れていたためでしょう。
また、向日葵が「遠くを見ていた」からと言って、それが帽子に見えることとの間には何の因果関係もありません。
初句から読んできて、それまでの部分が、結論の「帽子のごとし」に一直線につながる、それが短歌本来の構成であり、「遠く見ている」の主語が向日葵であるという説は誤りと思われます。
寺山修司の病気との関連
また、この歌と、寺山修司との病気に関連があるとも書かれていますが、その点についてはどうでしょうか。
この歌の作者は、寺山修司という人です。劇を書いたり小説を書いたり、短歌を作ったりします。この歌が発表されるちょっと前まで、ネフローゼという重い病気にかかって入院していました。夏に退院し、一度生まれ故郷の青森まで帰っています。その頃の歌だと考えられます。
この短歌は、「初期歌篇」に収められており、寺山を見出した当時編集長だった中井英夫によると、「初期歌篇」は15、6歳の高校生の時の作品です。
ネフローゼは、寺山修司を短命に終わらせた病気ですが、最初に診断を受けたのは18歳の時、大学に在学中だったので、罹患前の作品ということになりそうです。
寺山の最初の作品集『われに5月を』の観光は、21歳の時で、この本にも上記の作品は収められました。
青森への一次帰省は、年譜によると22歳の時。とすると、そもそも寺山が実生活を短歌に読むタイプの歌人だったかどうかを別としても、病気とこの作品の結びつきは関連はないと思われます。
一首の鑑賞
この歌のポイントはどこにあるのかというと、「少年」というモチーフを表現することです。
この短歌は章題が「森番」と題する項に収められています。
ねむりてもわが内に棲む森番の少年と古きレコード一枚
この少年は、「わが内に棲む」として、「少年=私」ではなく、私からやや距離を置いた存在として語られています。
他には、
日あたりて遠く蝉採る少年が駈けおりわれは何を忘れし
この少年も同様で、蝉を採る少年の姿や心に、私が忘れてしまったものがあるというところが主題です。
この歌にも「遠く」が使われています。
日向の光の中にいる少年は、もはや自分には遠い存在であるということなのです。
振り向けばすぐ海青し青春は頬をかすめて時過ぎてゆく
つまり、作者はやや大人びた存在であり、もはや自分が少年ではなくなりつつあることを感じている、それがこれらの歌の主題なのです。
最初の歌に戻って、もう一度思いを巡らすとすると
列車にて遠く見ている向日葵は少年のふる帽子のごとし
この歌の解釈をまとめると、
電車に向かって無邪気に帽子を振る少年、それはかつての私の姿だが、もう大人になりつつある私にとって遠い存在になってしまった。電車に乗って遠くに見える向日葵に、私は束の間少年であった自分の純真な心とその幻とを浮かべることができる。
つまり、過ぎていく少年時代への美しさ、表面に出ているのはそこだけですが、深く思いを巡らせれば、作者が自分の少年時代を哀惜していることが読み取れるのです。
この主題は、むしろこの歌一首よりも、一連の他の歌を通して読むとはっきり見えてきます。
寺山修司の他の向日葵の短歌
『空には本』より、他の向日葵の短歌を挙げておきます。*
枯れながら向日葵立てり声のなき凱歌を遠き日がかえらしむ
向日葵の顔いっぱいの種子かわき地平に逃げてゆく男あり
一粒の向日葵の種まきしのみに荒野をわれの処女地と呼びき
向日葵は枯れつつ花を捧げおり父の墓標はわれより低し――『空には本』
...
寺山修司プロフィール
寺山 修司(てらやま しゅうじ)1935年生
青森県弘前市生れ。 県立青森高校在学中より俳句、詩に早熟の才能を発揮。 早大教育学部に入学(後に中退)した1954(昭和29)年、「チエホフ祭」50首で短歌研究新人賞を受賞。 以後、放送劇、映画作品、さらには評論、写真などマルチに活動。膨大な量の文芸作品を発表した。
...
