正岡子規の有名な俳句にはどのようなものがあるでしょうか。
正岡子規が生涯に詠んだ俳句の数はたいへん多いので、その中からもっとも有名なもの、すぐれた作品を10句に選りすぐってご紹介します。
スポンサーリンク
正岡子規の俳句代表作10句
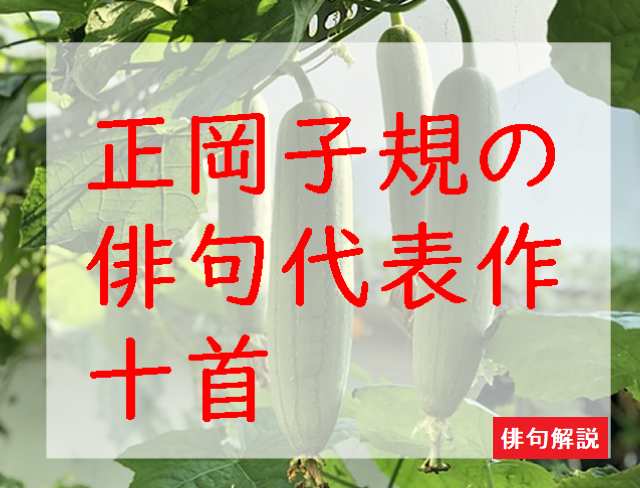
正岡子規は、生涯に20万を超える句を詠んだとされています。
その中でも、有名な俳句には下のようなものがあります。
※正岡子規について詳しく
正岡子規について 近代文学に短歌と俳句の両方に大きな影響
正岡子規の有名な俳句3作品
正岡子規のもっとも有名な俳句と言えば下の3つの句です。
柿くえば鐘がなるなり法隆寺
鶏頭の十四五本もありぬべし
いくたびも雪の深さを尋ねけり
それぞれの現代語訳をあげます。
柿くえば鐘がなるなり法隆寺
読み:かきく
現代語訳:
門前の茶屋で柿を食べていると鐘がなっている。法隆寺の鐘の音に秋を感じることだ
ワンポイント解説:
・2句切れ
・季語は「柿」で秋
・「食えば」は順接確定条件「~すると」
明治28年作、「法隆寺の茶店に憩ひて」という前書きがあります。
芭蕉の「古池や蛙飛びこむ水の音」と並んで俳句の代名詞として知られるほどに有名な俳句となっています。
※解説ページ
鶏頭の十四五本もありぬべし
読み:けいとうの じゅうしごほんも ありぬべし
現代語訳:
鶏頭の花が群れて咲いている。おそらく14、5本ほどあるだろう
ワンポイント解説:
・句切れなし
季語は「鶏頭」 夏
1900年9月作の題詠。
俳人の山口誓子は、この句について
鶏頭は14,5本として、全体的にとらえられている。だから、私はすぐ鶏頭の立ち並んでいる空間を感じ取り、その空間が14,5本の鶏頭をあらしめているのだと思った
と述べています。
斎藤茂吉は、子規の晩年の俳句でこの歌を第一に押しました。その理由は
この句の声調は実に短銃素朴で、もはや芭蕉でもなければ蕪村でもないものが根差している
というものです。
また斎藤茂吉はこの鶏頭の句から、子規の進むべき純熟の句が始まったと考えていました。
専門家には、評価がひじょうに高い俳句ですが、地味であるためか岩波文庫の「子規句集」にはおさめられていないようです。
※解説ページ
鶏頭の十四五本もありぬべし 正岡子規の句の意味と背景の解説
いくたびも雪の深さを尋ねけり
読み:いくたびも ゆきのふかさを たずねけり
現代語訳:
なんども繰り返し、雪の積もった深さを尋ねたのであったなあ。自分は寝たきりで起きられないので
ワンポイント解説:
・句切れなし
季語は「雪」 季節は冬
当時、東京、根岸の自宅で子規は妹と母と同居。妹律(りつ)に主に看病を受けていました。
後に、その部屋にはガラスが入れられましたが、その句を詠んだときは、まだ窓は障子のままであって、障子、防寒のために雨戸も占めてしまえば、外の様子が見えません。
雪の降る日に、雪の気配を感じたものの、寝たきりで動けない子規は、律に何度も訪ねていました。
雪が見えれば、雪を詠みたい。しかし、見えないので、雪を見たい、そのことそのものを句に詠んだのです。
※解説ページ
正岡子規の俳句 現代語訳
それ以外の7句は以下の通りです。
島々に灯をともしけり春の海
訳 春の海の島の一つ一つに火がともっているのだなあ
赤とんぼ筑波に雲もなかりけり
訳 赤蜻蛉が舞い飛ぶ筑波山の上に広がる空は雲一つない快晴であることよ
若あゆの二手になりてのぼりけり
訳 鮎達の群れが川の二手に分かれて上って行ったことよ
夏嵐机上の白紙飛び尽す
訳 夏の午後、突然に強い風が吹いて机の上の紙が全部飛び散ってしまった
春や昔十五万石の城下哉
訳 かつてはこの地も十五万石の栄えた城下だったが、その春も今は昔のことか
雪残る頂ひとつ国境
訳 国境の山の一つの頂きにだけ雪が残っている、もう春だ
紫陽花や昨日の誠今日の嘘
訳 紫陽花が咲いている。昨日は本当だといったことが今日は嘘になるように日々色を変えながら
正岡子規の糸瓜の絶筆三句
正岡子規が亡くなる前日に詠んだ糸瓜を主題とする3つの句は、「絶筆三句」と呼ばれています。
糸瓜咲て痰のつまりし仏かな
痰一斗糸瓜の水も間に合はず
をとゝひのへちまの水も取らざりき
正岡子規の命日は「糸瓜忌」と呼ばれます。
それぞれの俳句の現代語訳と解説は、下の個別の解説ページでご覧ください。
をとゝひのへちまの水も取らざりきの意味と解釈 正岡子規「辞世の句」
正岡子規の有名な短歌
子規の短歌については、下の記事をご覧ください
