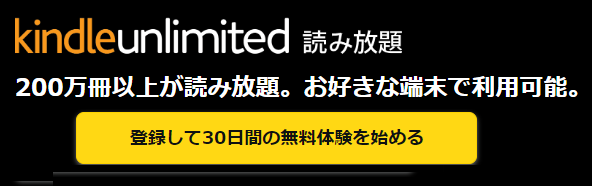津の国のこやとも人を言ふべきにひまこそなけれ葦の八重葺き 和泉式部
作者和泉式部の有名な和歌、現代語訳と句切れや修辞法の解説と鑑賞を記します。
スポンサーリンク
津の国のこやとも人を言ふべきにひまこそなけれ葦の八重葺き
読み:つのくにの こやともひとを いうべきに ひまこそなけれ あしのやえぶき
作者
和泉式部 いずみしきぶ
関連記事
出典
後拾遺集・恋二・六九一
関連記事
現代語訳と意味
津の国の昆陽ではないが「おいでなさい」というべきなのですが、人の目を盗む隙がありません。幾重にも葦を重ねた小屋であるように
句切れと修辞
- 句切れなし
- 掛詞
- 体言止め
- 係り結び
- 縁語
修辞解説
・「こや」の掛詞・・・昆陽(こや)という津の国の地名。他に「来や」と「小屋(家)」とをかけている掛詞。
・「ひまこそなけれ」の係り結び・・・「こそ・けれ」の係り結び
・「津の国」と「葦」は縁語
関連記事:
和歌の修辞法をわかりやすく解説
語の解説
- 津の国・・・摂津国(せっつのくに)いまの大阪と兵庫の一部
- こや・・・昆陽 ( こや ) は摂津国の歌枕。 行基が造った昆陽池や昆陽寺を中心とした一帯を指す
- ひま・・・暇 時間のいとま
- 葦・・・植物の一種で家の上部にかぶせて屋根とした
- 八重葺き・・八重は何重にも重ねたの意味 は屋根を形作る動詞「葺く」の名詞形
解説と鑑賞
和泉式部の技巧的な和歌で『俊頼髄脳』で和泉式部の歌として取り上げられた和歌。
藤原公任が絶賛したと言い伝えられている。
この和歌の特徴
相手に送る歌に歌枕を取り入れ、さらに掛詞や縁語を駆使した技巧的な歌であるところに特徴がある。
古くは和泉式部の代表作とされていた。
『俊頼髄脳』の記載
『俊頼髄脳』では「和泉式部と赤染衛門のどちらが優れた歌読みであるかを問われた公任が
「一言でどちらが良いといえるような歌人たちではない。和泉式部は『津の国のこやとも人を言ふべきに ひまこそなけれ葦の八重葺き』と詠んだ人である。とても素晴らしい歌人である」
と返答。
さらにその理由は
『こやとも人を』といってから、『ひまこそなけれ』という言葉は、凡人が思いつくことではない。すばらしいことだ。」
とほめたことによる。
和歌の歌枕
昆陽 ( こや ) は摂津国の歌枕。 行基が造った昆陽池や昆陽寺を中心とした一帯を指す。
歌の意味
『和泉式部集』には「わりなくうらむる人に」の詞書があり、自分を恨む人に送ったという歌であることがわかる。
歌の内容から「訪れるように」との誘いがないことを不満に思った相手に送る歌という前提である。
「津の国のこや」は、歌枕である昆陽(こや 摂津の地名)と「来や」と「小屋」を掛詞でかけたもので、「葦の八重葺き」はその小屋の屋根を表す。
八重は幾重にも葦を重ねたもので「隙間がない=時間の暇がない」ことが「ひまこそなけれ」の部分の意味となる。
この和歌の評価
この歌を「俊頼髄脳」で優れているとされるのは、やはり技巧が駆使されているためだろう。
特に挙げられている部分が「『こやとも人を』といひて、『ひまこそなけれ』といへる」になるが、やはり「昆陽」と「来や」の掛詞からさらに、葦の縁語を用いて相手に断りを述べるというつながりが感嘆の的となったようだ。
ただし、後に鴨長明が「無明抄」で和泉式部の代表作としたのが、「暗きより暗き道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月」であるように、必ずしもこの歌が高く評価されたわけではない。
和泉式部について
和泉 式部は、平安時代中期の歌人。
中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人.
すぐれた女流の抒情歌人として知られ、1500余首の歌を残した。
他に「和泉式部日記」がある。
和泉式部の他の和歌
今はただそよその事と思ひ出でて忘るばかりの憂きふしもがな
捨て果てむと思ふさへこそかなしけれ君に馴れにし我が身とおもへば
今宵さへあらばかくこそ思ほえめ今日暮れぬまの命ともがな
白露も夢もこの世もまぼろしもたとへていへば久しかりけり
とどめおきてだれをあわれと思ふらむ子はまさるらむ子はまさりけり