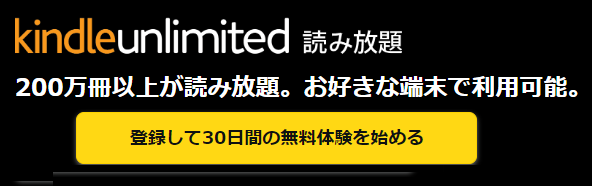その子二十櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな
与謝野晶子の歌集「みだれ髪」より、有名な短歌代表作品の現代語訳と意味、句切れと表現技法などについて解説、鑑賞します。
スポンサーリンク
その子二十櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな
読み:そのこはたち くしにながるる くろかみの おごりのはるの うつくしきかな
作者と出典

与謝野晶子『みだれ髪』
意味と現代語訳
その娘は今まさに二十歳。櫛に梳くとすべるように流れる黒髪を持つ、この誇りに満ちた青春のなんと美しいことだろう
語句・品詞
・初句6文字の字余り
・初句切れ
・「ながるる」は連体形で「黒髪」にかかる 下に解説。
「おごり」の意味
・「おごり」……おごりの漢字は数種ある
「驕り/奢り」は「いい気になること。思い上がり」の否定的な意味。
「奢り」は「ぜいたくなこと」で、ここではこちらの意味となる
・結句の「かな」は詠嘆の助詞
表現技法と句切れ
・「そのこはたち」の初句切れ、字余りは、いずれも「二十歳」の強調
「かかりうけ」の構成
・「櫛にながるる」は「黒髪」にかかり(修飾し)、「櫛にながるる黒髪の」は「おごり」にかかり、「櫛にながるる黒髪のおごりのは「春」にかかって、それぞれ続く名詞を形容する「かかりうけ」の構成
解説と鑑賞
この歌で一番の疑問が湧くとすると「その子」というのが誰かということで、一首だけの意味では、自分以外の二十歳の娘を描写し詠んだ歌となる。
しかし、歌集の題名が『みだれ髪』であることや、他にも髪を詠んだ歌があることからも、「その子」は作者自身でもあることがわかる。
この場合の「髪」の美しさはいわば若さの象徴であり、「その子」として第三者の立場から表したことから、一般的に二十歳の娘の持つ若さと美しさを表したものとして詠まれている。
自分自身のことを忌憚なく表せる歌となったため効果の大きなこの初句に作者の工夫があると言える。
「その子二十歳」の初句
さらに、表現技法としては、初句切れ、字余りの「その子二十歳」は強い印象を残す。
たとえばこれが「乙女らが」として始めた場合と比べてほしい
二十歳という年齢の区切り、「はたち」の音の歯切れの良さと共に、単に若いというよりも若年の範囲内でありながら円熟した最も美しい年齢という意味合いが込められている。
「櫛にながるる」は髪の長さ
「櫛にながるる」というのはそれ自体が髪の長さを表している。
それだけでなく、表現技法としては、上に述べたかかりうけ、「櫛にながるる」が「黒髪」に、「櫛にながるる黒髪の」が「おごり」に、「櫛にながるる黒髪のおごりのは「春」にかかって、言葉が続いていく様子が、どこまでも長くなって続いていく髪の長さを思わせる。
主語と動詞は「その子の若さが美しい」ということであって、それを表すのに髪という対象を用いているのであるが、単なる「髪」ではなく上記のような工夫があって、髪の美しさ、髪の豊かさという属性を表していることに大きな工夫がある。
「その子」は作者自身
与謝野晶子の短歌の現代語訳を試みた俵万智は、この歌の現代語訳の短歌を何と訳しているかというと、
「二十歳とはロングヘアーをなびかせて畏(おそ)れを知らぬ春のヴィーナス」
とている。
そこからみても、作者自身は曖昧にぼかされており、「その子」はやはり「私」や「われ」ではない。
しかし、二十歳になったばかりの自身の髪を梳き、その髪のつやつやと流れる美しい様子を見て、うっとりとしているのは、歌の前後を見てみても、やはり作者自身であるのだろう。
『みだれ髪』には他にも「その子ここに夕片笑みの二十びと虹のはしらを説くに隠れぬ」という「その子」の含まれる歌がある。
また、この歌の一連「臙脂紫(えんじむらさき」には「髪五尺ときなば水にやはらかき少女をとめごころは秘めて放たじ」が含まれておりいずれも髪が主体となっている。
なお、この「臙脂紫(えんじむらさき」は『みだれ髪』のもっとも最初の章となる。
※この歌の解説
髪五尺ときなば水にやはらかき少女ごころは秘めて放たじ 与謝野晶子解説
「おごりの春」とは
この歌で最も現代語で理解が難しいのが「おごりの春」のところだろう。
「おごり」というのは、この場合は「豪奢」(ごうしゃ)を指すのであるが、「驕り」ともとれるようなある種のナルシシズムもうかがえる。
実際にも与謝野晶子は、自分自身の黒髪を気に入っており、当時の髪の価値観もあって自慢できるものと考えていた。
それだから髪を「みだれ髪」歌集の題名にも入れている通りである。
あるいは、主語が作者自身であれば印象が強すぎるために、それをそらすために「その子」という主語を用いたのかもしれない。
そのために、主語が作者一人に限らず、二十歳一般と普遍の広がりを表すようになった。
したがって、この歌は背景を考えずとも、この歌一首のみで鑑賞ができるようにもなっている。
「みだれ髪」について
与謝野晶子は生涯で5万首の短歌を読んだが、最も有名だったのが処女歌集の『みだれ髪』である。
刊行と同時に大きな反響を巻き起こした『みだれ髪』は内容が恋愛を主題とした短歌が多く、当時としてはたいへんに大胆な、センセーショナルな内容だった。
与謝野晶子の歌の主題
奔放大胆な官能的な表現と、解放された自我の感情過多の表白、そもそもが主題が妻のあった与謝野鉄幹との不倫の恋愛であったため、このような内容が批判を受けたのは当然といえるだろう。
歌の良しあし以上にスキャンダルめいた印象を与えたので、『みだれ髪』はけして最初から高い評価を得たというわけではない。
『明星』と与謝野晶子の歌風
また、『明星』に現れる晦渋な比ゆ的、隠語的表現の多い独特な新しいスタイルを持つ新詩社の歌風も時代にそぐわないものとなったため、与謝野晶子自身がのちにかなりの歌を手直ししている。
しかし、鉄幹とのどうしても貫きたい恋愛とその意志表白は、作歌の大きなモチベーションとなったのは間違いない。
また、そのような空想的な傾向の強い『明星』に自由な投稿が許されたことで、与謝野晶子の才能が大きく花開いたと言える。
そもそも、これがアララギ派であったとしたら、そのような歌人同士の恋愛関係がそもそも成り立つはずはなかった。
結社と歌風の関連性についても考えさせられる。
与謝野晶子について
与謝野晶子(1878〜1942)
明星派の代表的な歌人。旧姓と名前は鳳(ほう)晶子。堺市生れ。堺女学校卒。
与謝野鉄幹の妻。新詩社の雑誌「明星」で活躍。大胆な恋愛を歌った歌集「みだれ髪」で一躍名を知られるようになる。生涯で5万首もの短歌を詠んだといわれる。他に訳に「源氏物語」。