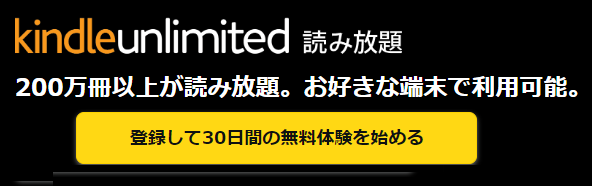菜の花がしあはせそうにきいろして 細見綾子の教材の俳句の切れ字や句切れ、擬人法の表現技法を含む意味の解説を記します。
スポンサーリンク
読み:なのはなが しあわせそうに きいろして
作者と出典:
細見綾子 「桃は八重 」
現代語訳
咲いている菜の花が黄色い色で なんとも幸せそうだ
表現技法
・擬人法
・「しあはせ」は、旧字で読みは「しあわせ」
切れ字と句切れ
切れ字なし
句切れなし
季語
季語は「菜の花」 春の季語
形式
有季定型
解説
菜の花を題材に現代の言葉、口語的に詠まれた新しい感覚の俳句。
菜の花は春に咲く代表的な花。栽培もされるが、道端で見かけることも多い身近な素朴な花である。
春は暖かくなった気候の中で誰しもが春の喜びに幸福感が兆す思いを味わったことがあるだろう。
作者は春の「菜の花」という季語を用いて、春に兆す幸せな気持ちを表現する。
「黄色して」の意味
結句は菜の花が「咲いている」ではなく、「黄色して」として、菜の花の色を強調。
明るい黄色の色に「幸せ」を象徴的に表している。
「黄色して」の文法
「黄色して」を文法で考えると「黄色い色をする」を短くした「黄色する」を、接続助詞「て」で終えたもの。
動詞の基本形ではないため、たとえば「黄色しぬ」とか「色づけり」というものよりも、「て」止めの方が、良い霧を避けて余韻があり、柔らかい感じが残る。
春の気候のほんのりとした温かさ、菜の花のほのぼのとした明るさを、表すのに「て」止めが大きな効果を与えている。
「黄色して」の擬人法
菜の花は、自ら黄色になるわけではないが、「菜の花が黄色をする」というのは、一種の擬人法であり、加えて菜の花が「幸せ」であるというのも、擬人法である。
黄色という色を幸せと結び付けるイメージをもって感じているのは、作者であり、それらの事物に託して、春という季節の持つ普遍的な幸福感を作者独自の感じ方として提示する。
-
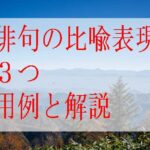
-
俳句の比喩表現3つ 用例と解説
俳句の比喩表現では、主に3つの種類の比喩、直喩と隠喩、魏婚法が使われます。 直喩と隠喩は「ごとく」や「ように」の語を使うか使わないかで違いが分けられます。 俳句の3つの比喩表現を用例をあげて解説します ...
続きを見る
私自身のこの俳句の感想
現代の俳句かと思ったら、昭和17年の句集の俳句で、その時代の俳句でもこのように新しい感覚の句であるところに惹かれました。「黄色して」は、話し言葉のようで俳句ではこれまで見たことのない表現です。柔らかい言い方で終わっているところも、ふんわりして魅力ある語法です。菜の花の黄色は当たり前ですが、そこに幸せを見る作者は繊細な感覚の持ち主だと思います。他の俳句にも似た着想の作品があり、親しみやすく、すぐに作者のファンになりました。
細見綾子の他の俳句
そら豆はまことに青き味したり
チューリップ喜びだけを持つてゐる
ふだん着でふだんの心桃の花
鶏頭を三尺離れもの思ふ
細見綾子について
細見綾子(1907年3月31日 - 1997年9月6日)は、兵庫県出身の俳人。医師の夫が結核で亡くなり、自らも肋膜炎を病み、句作を始める。1952年、第2回茅舎賞、1975年、句集『伎芸天』で芸術選奨文部大臣賞、1979年、句集『曼陀羅』他の業績により蛇笏賞、1981年、勲四等瑞宝章を受章する経歴を持つ。
教科書の俳句一覧
教科書掲載の俳句一覧です。
各俳句の解説はリンク先の記事で読めます。
斧入れて香におどろくや冬木立 与謝蕪村
桐一葉日当りながら落ちにけり 高浜虚子
秋つばめ包のひとつに赤ん坊 黒田杏子
ぬうぬうと秋かき混ぜる観覧車 藤本敏史
林道の朽ちし廃バス額の花 村上健志
囀りをこぼさじと抱く大樹かな 星野立子
菜の花がしあはせさうに黄色して 細身綾子
谺して山ホトトギスほしいまま 杉田久女
万緑の中や吾子の歯は生え初むる 中村草田男
芋の露連山影を正しうす 飯田蛇笏
星空へ店より林檎あふれをり 橋本多佳子
いくたびも雪の深さを尋ねけり 正岡子規
小春日や石を噛み入る赤蜻蛉 村上鬼城
分け入つても分け入つても青い山 種田山頭火
入れものがない両手で受ける 尾崎放哉
※他の教科書の俳句を読む
教科書の俳句 中学高校の教材に掲載された有名な俳句一覧 解説と鑑賞