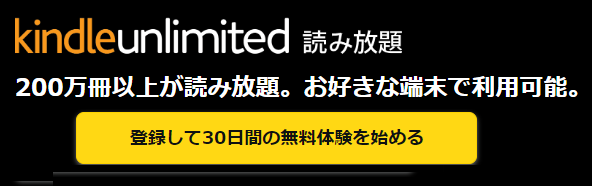桐一葉日当りながら落ちにけり 高浜虚子の教科書掲載の俳句、作者が感動したところや心情を詳しく解説・鑑賞します。
スポンサーリンク
桐一葉日当りながら落ちにけり
読み:きりひとは ひあたりながら おちにけり
作者と出典:
高浜虚子
現代語訳
桐の木から一枚の葉が日差しを受けながら落ちていったよ
句切れと切れ字
句切れなし
切れ字「けり」
季語
季語は「桐一葉」 秋の季語
形式
有季定型
解説
高浜虚子の教科書掲載の俳句。
桐の落ち葉が落ちていく様子を詠み、情景描写が注目される。
桐の葉の特徴

桐は、日本に古くからある木で、そこから採れる板は下駄や箪笥など身近なものに使われたことで知られている。
桐の大きな薄い葉には特徴があり、落ち葉となった時は、ひらひらと舞うように落ちる。
作者の感動の中心と思い
作者の感動の中心は、「日当たりながら」にある。
桐の葉が、落ちるときは、まっすぐ下に落ちるのではなくて、風を受けて翻りながら落ちる。
そこに、陽ざしが当たって、葉の裏表と光の明暗に作者が注目したところに、この句のポイントがある。
実際に桐の葉が落ちるまでの時間は短いが、この句では、まるでスローモーションであるかのように、桐の葉の落ちる様子を表している。
その、光と葉の戯れの様子に、作者はまた、秋という季節をも感じ取って表している。
私自身のこの俳句の感想
初句の「桐一葉」(きりひとは)の5文字の音が美しく印象的で、まずそこをぱっととらえて視線を向ける作者が感じられます。次いで「日当たりながら落ちにけり」12文字は、桐の葉の動きを表しています。12文字の方が長いので、桐の葉がゆっくりと落ちる時間の経過が感じられるのはそのためだと思います。
高浜虚子の他の俳句
教科書の俳句一覧
教科書掲載の俳句一覧です。
各俳句の解説はリンク先の記事で読めます。
斧入れて香におどろくや冬木立 与謝蕪村
桐一葉日当りながら落ちにけり 高浜虚子
秋つばめ包のひとつに赤ん坊 黒田杏子
ぬうぬうと秋かき混ぜる観覧車 藤本敏史
林道の朽ちし廃バス額の花 村上健志
囀りをこぼさじと抱く大樹かな 星野立子
菜の花がしあはせさうに黄色して 細身綾子
谺して山ホトトギスほしいまま 杉田久女
万緑の中や吾子の歯は生え初むる 中村草田男
芋の露連山影を正しうす 飯田蛇笏
星空へ店より林檎あふれをり 橋本多佳子
いくたびも雪の深さを尋ねけり 正岡子規
小春日や石を噛み入る赤蜻蛉 村上鬼城
分け入つても分け入つても青い山 種田山頭火
入れものがない両手で受ける 尾崎放哉
※他の教科書の俳句を読む
教科書の俳句 中学高校の教材に掲載された有名な俳句一覧 解説と鑑賞