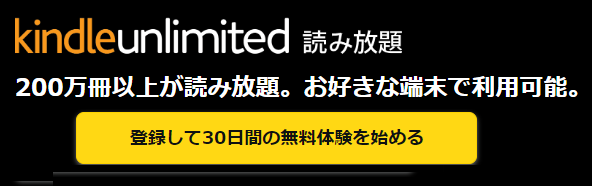芋の露連山影を正しうす 作者飯田蛇笏の教材の俳句の意味の解説、鑑賞を記します。
スポンサーリンク
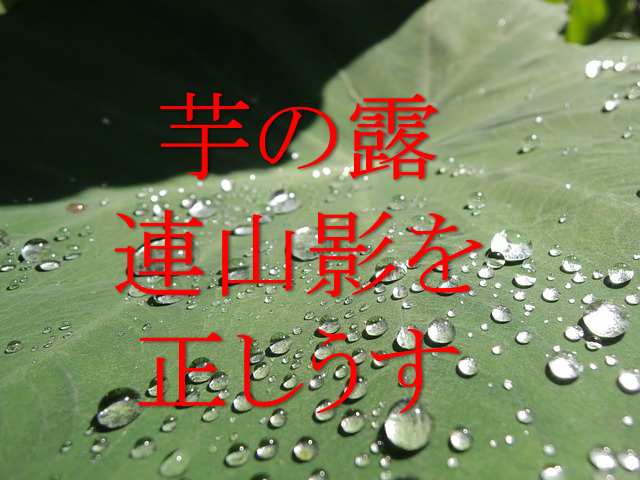
現代語での読みと発音:
いものつゆ れんざんかげを ただしゅうす
作者と出典:
飯田蛇笏 『山廬集』
現代語訳
芋の葉の上に光る小さな露、その向こうの遠くには山々が威厳をもってそびえていることだ
句切れと切れ字
・初句切れ
・切れ字なし
季語
・季語は「芋」「露」「芋の露」
「芋」「露」「芋の露」とも「秋」の季語
形式
有季定型
表現技法
擬人法
-
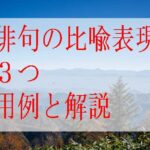
-
俳句の比喩表現3つ 用例と解説
俳句の比喩表現では、主に3つの種類の比喩、直喩と隠喩、魏婚法が使われます。 直喩と隠喩は「ごとく」や「ように」の語を使うか使わないかで違いが分けられます。 俳句の3つの比喩表現を用例をあげて解説します ...
続きを見る
語句と文法
・連山…連なった山々。連峰。この句では、山梨県の日本中央高地の山々とされている。
影の意味
「影」の辞書の定義では
光によって、その物のほかにできる、その物の姿
のこと。(広辞苑、第6版より)
「正しうす」の品詞分解
読みは、「ただしゅうす」。
「す」はサ変動詞で意味は、「する」
「正しう」の基本形は、「正し」の形容詞だろう。
形容詞の「正し」の「きちんとしている」との広辞苑での定義が最もよくあてはまるだろう。
「正しくする」が元の形で、その文語形のウ音便が「ただしゅうす」となると思われる。
他に、動詞「正す」「正す」の意味は、「正しくする。改めなおす」で、作者はこちらの意味をも込めたという人もいる。
解説
飯田蛇笏のもっともよく知られる俳句で、代表作の一句。
作者の感動の中心
秋の山辺の冷涼爽快な空気の中に、南アルプスの山並みのくっきりとした姿が、威厳をたたえながらそびえている様子に作者は感動を覚えている。
表現技法
一句の表現技法と特徴について。
「芋の露」の情景の意味
里芋の葉は表面に細かい毛が生えており、露の水玉ができやすい構造となっている。
露ができる季節は多くは秋で、寒暖差の大きなときにできやすい。
「芋の露」を初句に置いた目的は、秋という季節とその冷涼な気候を表している。
澄んだ空気の中にこそ、遠くにあるものは、くっきりと見えることを前提に、露をまず置き、そのあとに連山が続く順序になっている。
露と連山の対比
その他にも、露はそのあとにくる山との対比がある。
この露、すなわち水玉は作者の歩いている道ぞいに見える小さなものである。
視点の近くと遠く、小さいものと大きなもの。
露と対比して、山々の姿を並置、その雄大さを強調している。
さらに、露というものは、朝にできて日が高くなると消えてしまうはかないものである。
露の意味は、はかなさの対極にある、どっしりとそびえて長い年月を飼わることのない山並みとの対照にもあるだろう。
助詞の省略
「芋の露」の露は名詞。
あえて助詞を加えるとするなら、「芋の露に」の「に」が考えられる。
そのあとは、「露」の名詞の後「連山影」と続くがこの部分も「連山が影」と「の」を補って考えることができる。
助詞を省いた言葉の音調は、山のくっきりとした威厳のあるイメージにつながる。
擬人法
この句では、「山」を主語にした擬人法が用いられている。
「連山」の動詞として選び取ったのが、この句では「正しうす」であり、特殊な動詞といえる。
飯田蛇笏は山を擬人化することで、あたかも人と同じような意思を持ったものとして扱うことで、山への尊敬の念を表し、山の威容を高めている。
たとえば、以下の2つの言い方を比べてみよう
- 山が映っている
- 山が影を律している
「山が映っている」といったとすれば、これは、そのような状態や現象を客観的に述べたに過ぎない。
「山が自らの影をも律している」といったとすれば、その影にまでも価値を与えていることになり、それは「山」の意思的な所作となるだろう。
飯田蛇笏自身の解説
作者自身は「自選自註五十句抄」で下のように
今日に至るまでの歳月の中で最も健康がすぐれなかった時である。隣村のY-医院へ毎日薬壜を提げて通っていた。南アルプス連峰が、爽涼たる大気のなかに、きびしく礼容をととのえていた。身辺の植物(植物にかぎらず)は、決して芋のみではなかったのである。-(飯田蛇笏集成 第五巻鑑賞Ⅱ 自選自註五十句抄)
飯田蛇笏の他の俳句
月の窓にものの葉うらのほたるかな
蚊ばしらや眉のほとりの空あかり
雷のあと日影忘れて花葵
雷やみし合歓の日南の旅人かな
飯田蛇笏について
読みは、いいだだこつ。本名は武治。山梨県生まれ。早稲田大学中退。芭蕉に傾倒して、高浜虚子の指導を受ける。衆生てきて雄勁荘重な工夫を樹立。句集「山蘆集」「山響集」他。
教科書の俳句一覧
教科書掲載の俳句一覧です。
各俳句の解説はリンク先の記事で読めます。
斧入れて香におどろくや冬木立 与謝蕪村
桐一葉日当りながら落ちにけり 高浜虚子
秋つばめ包のひとつに赤ん坊 黒田杏子
ぬうぬうと秋かき混ぜる観覧車 藤本敏史
林道の朽ちし廃バス額の花 村上健志
囀りをこぼさじと抱く大樹かな 星野立子
菜の花がしあはせさうに黄色して 細身綾子
谺して山ホトトギスほしいまま 杉田久女
万緑の中や吾子の歯は生え初むる 中村草田男
芋の露連山影を正しうす 飯田蛇笏
星空へ店より林檎あふれをり 橋本多佳子
いくたびも雪の深さを尋ねけり 正岡子規
小春日や石を噛み入る赤蜻蛉 村上鬼城
分け入つても分け入つても青い山 種田山頭火
入れものがない両手で受ける 尾崎放哉
※他の教科書の俳句を読む
教科書の俳句 中学高校の教材に掲載された有名な俳句一覧 解説と鑑賞