-

-
夏至の短歌 一年で昼が最も長い日を詠む
2023/6/22 日めくり短歌
夏至というのは、昼が最も長くなること。何となく不思議な日に思われますね。 きょう、夏至の日の日めくり短歌は、夏至をテーマに詠んだ短歌をご紹介します。
-

-
天声人語に父の短歌「世の娘半分は父を嫌ふとぞ猫を撫でつつ答へむとせず」
2021/6/20 日めくり短歌
父の短歌、父親の短歌、きょう父の日は、朝日新聞の「天声人語」に父の短歌が紹介されました。 父の立場から詠んだ歌を含め、父に関わる短歌の数々をご紹介します。
-
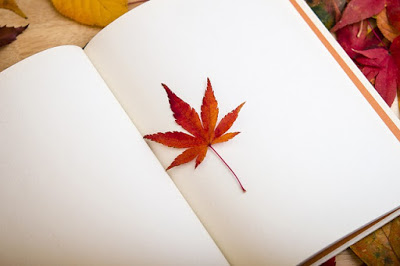
-
難波潟短かき蘆の節の間も逢はでこの世を過ぐしてよとや 伊勢
2022/12/18 百人一首
難波潟短かき蘆の節の間も逢はでこの世を過ぐしてよとや 百人一首に採られた女流歌人、伊勢の有名な和歌、現代語訳と句切れや係り結びの修辞法の解説と鑑賞を記します。
-
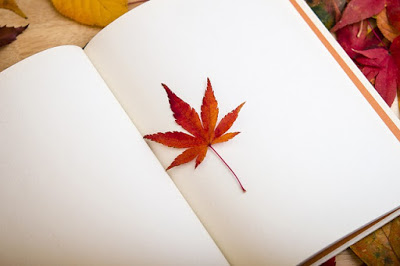
-
秋風にたなびく雲のたえ間よりもれいづる月の影のさやけさ 左京大夫顕輔
秋風にたなびく雲のたえ間よりもれいづる月の影のさやけさ 百人一首に採られた左京大夫顕輔(さきょうのだいぶあきすけ)、藤原顕輔、の有名な和歌、現代語訳と句切れなどの修辞法の解説と鑑賞を記します。
-

-
道にあひて咲まししからに降る雪の消なば消ぬがに恋ふといふ吾妹 聖武天皇
2022/8/14
道にあひて咲まししからに降る雪の消なば消ぬがに恋ふといふ吾妹 聖武天皇の万葉集の短歌の現代語訳、句切れや語句、品詞分解を解説、鑑賞します。
-

-
織田信長の「敦盛」 辞世の句とされる「人間五十年」の意味
2021/6/2 辞世の句
織田信長は最期に「人間五十年」で始まる幸若舞「敦盛」を舞ったとされています。 この「人間五十年」が織田信長の辞世の句ともされています。 きょうの日めくり短歌は「本能寺の変」にちなみ、織田信長の辞世の句 ...
-

-
与謝野晶子と与謝野鉄幹 「二人三脚」でたどり着いた常世の春
2021/5/29 日めくり短歌
与謝野晶子は、歌誌『明星』の主催者であった与謝野鉄幹によって見いだされ、歌人の地位を築きました。 その後の与謝野鉄幹と晶子の生活は「二人三脚」であったと言われています。 きょうの日めくり短歌は、与謝野 ...
-
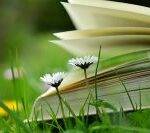
-
『風立ちぬ』「いざ生きめやも」の正しい意味 堀辰雄の誤訳の理由
2023/6/5 文学
堀辰雄の代表作の小説『風立ちぬ』の詩文「風立ちぬ いざ生きめやも」の意味は「生きられはしない」であり、「いざ生きめやも」は堀辰雄の誤訳といわれています。 「いざ生きめやも」の「やも」部分の反語表現につ ...
-

-
平塚らいてう「元始、女性は太陽であった」『青鞜』序文の意味をわかりやすく解説
2022/5/24 文学
平塚らいてうの今日は「らいてう忌」。平塚らいてうは月刊文芸誌『青鞜』を発行、その冒頭に記されたのが、「元始、女性は太陽であった」との”名言”です。 平塚らいてうの記した、「元始、女性は太陽であった」の ...
-

-
『青鞜』の序文全文 平塚らいてう著 「元始、女性は太陽であった」
2022/5/24 文学
『青鞜』を発行したのは平塚らいてう、その冒頭序文に記されたのが、「元始、女性は太陽であった」との”名言”です。 『青鞜』の序文全文を掲載します。
-

-
「ますらをぶり」と「たをやめぶり」賀茂真淵のいう意味と作品例
2021/5/15
「ますらをぶり」と「たをやめぶり」というのは、万葉集と古今和歌集の作品を対比させてその特徴を言う時の言葉です。 提唱したのは賀茂真淵と本居宣長。「ますらをぶり」と「たをやめぶり」、それぞれの言葉の定 ...
-

-
万葉集 最初の巻頭歌 「籠もよみ籠持ち」雄略天皇作長歌
2022/8/14
万葉集 最初の歌は、「籠もよ み籠持ち ふくしもよ みぶくし持ち 」で始まる作者雄略天皇と記される長歌です。 万葉集にいくつかある伝承歌の一首である巻頭歌の内容を解説します。
-

-
うつせみのわが息息を見むものは窗にのぼれる蟷螂ひとつ 斎藤茂吉『小園』
2021/6/4
うつせみのわが息息を見むものは窗にのぼれる蟷螂ひとつ 作者は斎藤茂吉、第十五歌集『小園』より、疎開先の蔵座敷で蟷螂に話しかけるように詠まれた代表作の短歌の解説と観賞を記します。
-

-
秋の日の穂田を雁がね暗けくに夜のほどろにも鳴き渡るかも 聖武天皇
2022/10/1
秋の日の穂田を雁がね暗けくに夜のほどろにも鳴き渡るかも 作者聖武天皇の万葉集の短歌の現代語訳、句切れや語句、品詞分解を解説、鑑賞します。
-

-
白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝はつめたき水くみにけり 長塚節
2022/2/8 長塚節
白埴の瓶こそよけれ霧ながら朝はつめたき水くみにけり 長塚節の歌集『鍼のごとく』にある代表作短歌を解説、鑑賞します。 国語の教科書や教材に取り上げられる作品です。
-

-
みづうみの氷は解けてなほ寒し三日月の影波にうつろふ 島木赤彦
2021/5/2 島木赤彦
みづうみの氷は解けてなほ寒し三日月の影波にうつろふ 島木赤彦の教科書や教材にも取り上げられている代表的な短歌作品の現代語訳と句切れと語句を解説します。